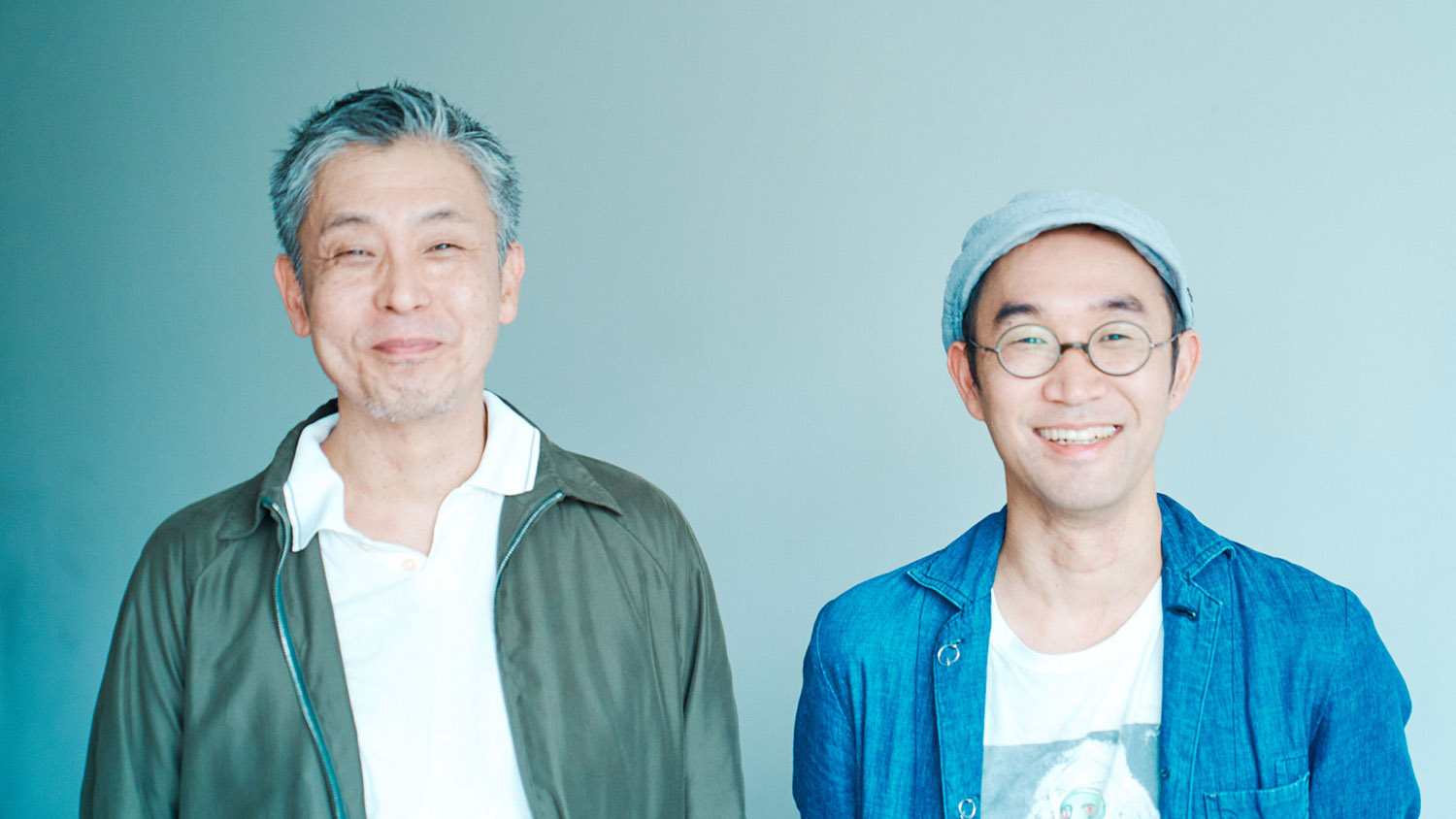目次

立山の麓で感じた「生死の遠近感」
― 本作は、立山連峰の麓にある「芦峅寺(あしくらじ)」という集落で誕生した、女人救済の儀式「布橋灌頂会」がモチーフとなっています。坂本監督はこれまでも、富山を舞台に、そこに生きる人々の営みや自然との関わりを描かれてきました。
― デビュー作『真白の恋』(2017)でも立山連峰を撮られていますが、今作を撮影するにあたり改めて立山を歩かれたそうですね。
坂本 : はい。「芦峅寺」は立山の中でも、少し異質と言いますか、特別な感じのする場所で。富山で暮らしていても、実はあまり馴染みのない場所だったんです。
― 坂本監督は富山で生まれ、大学入学のために上京するまで、富山で過ごされていました。「芦峅寺」は、今作の撮影にあたり初めて訪れたのでしょうか。
坂本 : はい。『真白の恋』の公開準備をしている頃に、地元のアナウンサーから「布橋灌頂会」の話を聞いたことがきっかけでこの儀式に興味を持ち、初めて訪れました。ロケハンでは、立山の一部の立ち入り制限区域にも、特別に許可をもらって歩かせてもらったんです。歩きながら土地の雰囲気を吸収していった感じですね。
― 立山は、富士山・白山と並んで「日本三霊山」のひとつに数えられ、1300年前から続くといわれる山岳信仰の舞台のひとつでもあります。
― 渡辺真起子さん演じる主人公・由起子は「布橋灌頂会」に参加した帰り道、地元の高校生・沙梨(陣野小和)と出会い、共に山を降っていきますが、その道中は現実の風景でありながら、まるで「あの世とこの世の間」を歩いているかのようで強く印象に残りました。
坂本 : あの道中の撮影場所は、撮影の米倉さんと一緒に歩き、人の気配を極力排除できる場所を探しました。芦峅寺周辺は、皆さんも実際に訪れると「おぉ」と感じるような土地だと思います。雄山山頂にある「雄山神社 峰本社」などは、パワースポットとしても有名な場所ですから。
― 劇中、由起子は「小元」というバス停を起点に歩き始めますが、あの場所は実際には…?
坂本 : この映画のためにつくった、架空のバス停なんです。
渡辺 : 現実にあるかのような存在感でした。
― 渡辺さんは由起子として立たれてみて、いかがでしたか?

渡辺 : 山に包まれている、という感覚がありました。立山連峰に囲まれた、広大な空間がそこにあって、その中に私がいるという感覚です。
芦峅寺に入ると、立山連峰がすごく綺麗に見えるんです。深い山々が開けていて、その遠近感がとても美しい。その風景を見ていると、その「遠近感」が自分の中にも小さくあるように感じられました。
― 「自分の中に小さくある遠近感」、ですか?
渡辺 : はい。「生死」も、遠近感で語れるのではないかと思うんです。オギャーと生まれた瞬間にはわからないけれど、人生を重ねる中で、「死」が自分の中で近くなったり、遠くなったりする。そんな感覚です。

― 由起子が「布橋灌頂会」に参加するきっかけのひとつとなった「立山曼荼羅(たてやままんだら)」にも描かれているように、立山は、穢れを落とし、生まれ変わるための登山道「禅定登拝道」としての歴史がある場所でもありますね。
渡辺 : 芦峅寺の方たちは、自分たちの土地の歴史や、これまでどう生きてこられたのかを、私たちにわかりやすく話してくださいました。とてもいい方ばかりで。
例えば、明治政府の神仏分離令(※)が出された時、神仏が混淆していた芦峅寺では仏像やお地蔵様、石仏を保存することにつくした、ということも教えていただきました。
※神仏分離令…明治政府が発令した、日本の伝統的な信仰である神道と仏教を明確に区別させる政策。これにより、多くの寺院や仏像が破壊された。
― 芦峅寺は、立山信仰の案内人である「衆徒(しゅうと)」として、参拝者を山へ導いた歴史がある集落でもあります。そういうお話は撮影の合間にお伺いになったんでしょうか。
渡辺 : そうですね、支度場所などをお借りしたので。私たちが自分の家みたいに寛がせていただいた場所があるんですけど、そのお宅のお母さんが、「私たちがここにいることを知ってほしい」とおっしゃっていたのが心に残っています。
その言葉は、由起子がコツコツと生きる毎日の中で、自身の存在を問う気持ちと、どこか繋がるように感じたんです。

「渡辺真起子・主演で、映画を撮りたい」
― 今作は「渡辺真起子さん主演」を前提に企画を進められたそうですね。前作の『もみの家』(2020)の撮影中に、坂本監督は渡辺さんに直接その思いを伝えられたと伺いました。渡辺さんのどのような点に惹かれ、「主演に」と強く思われたのでしょうか。
渡辺 : 忌憚のないご意見を。
坂本 : はい(笑)。僕は中・高校生の時に観た映画が、今の自分に大きな影響を与えているんですけど、その一本が『独立少年合唱団』(2000)という映画なんです。
― 第50回ベルリン国際映画祭でアルフレート・バウアー賞に輝いた、緒方明監督の劇場映画デビュー作ですね。学生運動に揺れる1970年代を舞台に、合唱部員の少年二人の友情を描いた青春映画です。
坂本 : でも、正直なところ、当時の僕にはよく理解できなかった。それで、何度も繰り返し観ました。高校1年生ぐらいの時ですかね。クレジットにあった「サンセントシネマワークス」という会社の名前が記憶に残り、そこから夏休みになると、「新作」か「ジャケットがかっこいい映画」、または「サンセントシネマワークス配給の映画」を借りて観るようになりました。

坂本 : その中の一つに、渡辺さん主演の映画『M/OTHER』(1999)があったんです。
― 第52回カンヌ国際映画祭で国際批評家連盟賞受賞した、諏訪敦彦監督の長編第二作で、渡辺さんは三浦友和さんと共に年の離れたカップルを演じられました。
坂本 : その後、映画監督を目指して専門学校に通うようになるんですけど、先生から勧められて観に行く映画の多くに、渡辺さんが出演されていて。映画を観た後に、友人たちと「渡辺さん、かっこよかったね」と話したのが2008年の夏。
僕は、「僕が観た映画の中の渡辺真起子」が忘れられなくて、その頃から、いつかこの人と映画を撮りたいとずっと思ってきました。
渡辺 : そうなの? 初めて聞いた。
坂本 : 『もみの家』に渡辺さんに出演していただく際も、プロデューサーに懇願して。そしたら、念願が叶って出演していただくことになって。
撮影現場で渡辺さんは「こうするのは、どうですか?」と意見を伝えてくださるんです。ディスカッションしながら作品をつくりあげたという経験が、僕の映画制作人生で、とても大きなものになって。「渡辺さん主演で映画をつくりたい」という思いがより一層強くなりました。

― 『もみの家』の撮影の中で、その思いを坂本監督から伝えられた時、渡辺さんは率直にどう感じられましたか?
渡辺 : 「へー、そう」って。
一同 : (笑)。
坂本 : 車で移動中に「布橋灌頂会という儀式があって…」と映像を見せて、渡辺さん主演で撮りたいとお伝えしたら、「俳優の〇〇さんがいいんじゃない?」っておっしゃって…。あんまり前向きじゃなかったのかな、と。渡辺さんは覚えてないかもしれないんですが…。

渡辺 : そうそう、言った(笑)。いや、そこには理由がありまして。映画の企画って、なかなか実現しないことが多いんです。皆さん「いつかご一緒したい」って言ってくださるんですけど、話が具体的になるまでは期待しない癖がついているんです。
そうしないと、心が壊れちゃうから。俳優って、やっぱり請け負う仕事じゃないですか。だから、自分の心を健全に保ちながら、この仕事を続けていくためには、どうしても客観的な視点が強くなってしまう。
― なるほど。
渡辺 : 「布橋灌頂会」にすごく興味もあったし、映像も美しかった…。でも、私でいいのかなっていう思いもありました。だから、そこら辺は曖昧に。もちろん照れもありましたけど…って私、何言ってるんだろう(笑)。
― では、脚本と共に改めて依頼があった時は。
渡辺 : 「ほぅ」と。
一同 : (笑)。
― 娘を亡くし、15年間も深い喪失と自責の念を抱え続ける由起子という役を演じられるということについては、いかがでしたか?

渡辺 : 私は57歳なんで、何かを失った経験はあります。それは生きていく上で普通のこと。だから、由起子のことを「わかる」とは言えないけれど、「わからない」わけではない。私の中にもあることかなと。
それをわざわざ人に語ったりはしませんが。でも、その喪失を「なかったこと」にはできない。それを乗り越えて、由起子は先に進んできたのだろうと考えながら歩いていただけで、特別に「役作り」はしてないです。
― はい。
渡辺 : 役は一人でつくるものではなく、脚本や演出、関わるみんなでつくりあげていくものなのではないかと思います。この物語を立ち上げたいという思いで、みんなのそばにしっかりといること。それが一番の役作りになるんじゃないかなと考えていました。

「神が住む山」に流れる
大きな時間軸の中で
― 由起子が再生に向かう大きなきっかけとなる「布橋灌頂会」は、橋のこちら側を「この世」、渡った先を「あの世」と見立て、橋を渡ることで死を疑似体験し、そこから蘇って生きる力を得る「生まれ変わり」の儀式です。

― 声明と雅楽、自然の音が渾然一体となる中、白装束を纏った女性たちが目隠しをして橋を渡っていく。その光景は圧巻でした。
渡辺 : 橋の向こう側にいる僧侶「来迎衆」に、橋の中央で案内役の「引導衆」から引き継がれる瞬間があるんですが、それがもう、すごくて…。
私たちはどこかに踏み込むんでいくんだな、と。どうやら橋を渡るだけじゃなく、どこかに連れて行かれるらしい…「どこに連れていくんだ、私を!」って(笑)。そんな話、聞いてませんでしたから!
― 橋を渡った後に「遙望館」の中に入っていくことは、ご存知なかったんですか!? それは、坂本監督の演出だったんでしょうか?
渡辺 : わざとだった?

坂本 : すいません…知ってるもんだと勝手に…。
渡辺 : 知りませんでした! お堂に入っていくと真っ暗闇で、「何にも見えない!」って、本当に驚きました(笑)。
― 参加した女性たちは、遙望館の暗闇の中で目隠しを外し、一心に祈りを捧げた後、正面の戸が開け放たれる「御開帳」で立山連峰を拝みます。儀式の、そして今作のクライマックスでもありますね。
渡辺 : 何も知らされずにその瞬間を迎えたので、どんな気持ちで立山連峰を見ればいいのかと。エキストラとして参加してくださった地元の方たちが、儀式やその反応について教えてくださったので、それに照らし合わせながら、自分の人格をギリギリに保ちながら(笑)、シーンとしてやるべきことに徹しました。
渡辺 : でも、撮影はてんやわんやだったんですが、僧侶の方々はとても落ち着かれていて、信仰や儀式について何を聞いても優しく説明してくださったので、大変助かりました。
その時に、立山で観測される「ブロッケン現象」の話を伺ったんです。太陽を背にした時、自分の影の周りに虹色の光の輪が見える現象のことで、日本ではそれを仏様が後光を放ちながら姿を現す「御来迎(ごらいごう)」と呼んで、神聖視してきたそうなんです。
― それが立山信仰の原点にも繋がっているんですね。
渡辺 : 陽を背にして、パッと自分の影を見たら、そこに仏様がいる。「布橋灌頂会」でお堂から立山連峰の姿に極楽浄土を見てとり、心を新たにするというのも、そのリアルな体験に近い感覚なのではないかと感じました。
― その「御開帳」までのシーンは、映画を観ている側も儀式を追体験しているような感覚になりました。
坂本 : 僕は2023年に開催された際に、本来、遙望館は男性禁制なのですが、町長から特別に許可を得て、中に入らせていただいたんです。その時は撮影のことを考えていたはずなのに、気づけば自分のこれまでの行いや映画との向き合い方について、懺悔のような気持ちが巡ってきて…。

坂本 : このリアルな体験を、映画の中に落とし込みたいと思いました。でも、一番大変だったのは、この儀式を再現するために、多くの方々から許可をいただくことでしたね。儀式を執り行う僧侶の方は、県外在住の方がほとんどだったので、本作の撮影のためにわざわざ富山まで集まっていただいたんです。
渡辺 : 女人衆としてエキストラ出演してくださった立山町の方々や雄山高校の皆さんをはじめ、本当に多くの方が協力してくださいましたよね。それで思い出したのが、儀式の待機時間などにエキストラとして参加してくださった地元の方たちが交わす、ごく普通の日常会話です。荘厳な儀式の「非日常的な時間」と並行して、「日常の時間」も確かに流れていて。
その対比があるからこそ、儀式に参加する一人ひとりが、より際立った「個」になっていくじゃないかなと感じました。
― 儀式という特別な「ハレ」の時間と、日常である「ケ」の時間が、同時に存在していたのですね。
渡辺 : この土地にとって、立山信仰とは日常の延長にあるものなんだろうと感じましたね。

渡辺真起子、坂本欣弘監督の「心の一本の映画」
― 坂本監督は、『真白の恋』『もみの家』そして今作『無明の橋』と、一貫して「自分という存在に罪の意識を抱えている主人公が、自然や人の営みに触れ、回復していく過程」を描かれてきました。そこにはどのような思いがあるのでしょうか。
坂本 : そうですね。自分がこれまでにそういう映画に励まされ、「もう少し頑張ってみよう」と思える体験があって…そうなんですよね、それで映画をつくりたいって思って。そういう原体験があります。
20歳ぐらいの時に、「どういう映画をつくっていきたいか」を考えたことがありました。例えば、死にたいと思って東尋坊へ向かう道中で、ふと立ち寄った蕎麦屋さんのテレビでたまたま流れていた「金曜ロードショー」を観て、「明日も生きてみよう」と思ってもらえるような、そういう映画をつくりたい。それが、自分の映画監督のスタート地点なんです。

坂本 : 映画の専門学校の卒業制作も、根底には同じ思いがあったんですが、先生から「死を扱う時は、生半可な気持ちでやるな」と言われて。それ以来、正面から描くことはしてこなかったんですが、今回は覚悟を決めてそこに向き合おうと思いました。
渡辺 : いい先生だね。
― では最後に、お二人の「心の一本の映画」を教えてください。坂本監督がおっしゃっていたように、今作が目指した「観た人の道標になるような映画」や、今作を観た人におすすめしたい映画があれば、教えてください。
坂本 : 『バーニング 劇場版』(2018)ですね。
渡辺 : イ・チャンドン監督のね。
坂本 : この映画は渡辺さんに「これを観ろ!」と言われて観たんですが、観終わった後、自分の中にフワッと入ってくるものがあったんです。その感覚を、この映画にも少しでも入れられたらいいなと思っていました。
渡辺 : 私、立派。いいこと言ったね。
坂本 : はい(笑)。
渡辺 : この映画は内省していく作品なので、「外に向かっていく映画」をおすすめしますね。レオナルド・ディカプリオ主演の『ワン・バトル・アフター・アナザー』(2025)です。
― ポール・トーマス・アンダーソン監督の最新作で、冴えない日々を送る元革命家の主人公が、ある日娘をさらわれたことを機に、昔の闘争心を甦らせていく姿を描いた作品です。
渡辺 : 最高に面白かったです。全部吐き出すような、ありのままの素敵なオヤジたちを観て、スカッとするのもいいんじゃないでしょうか。ヒロイン像もかなり強いです。