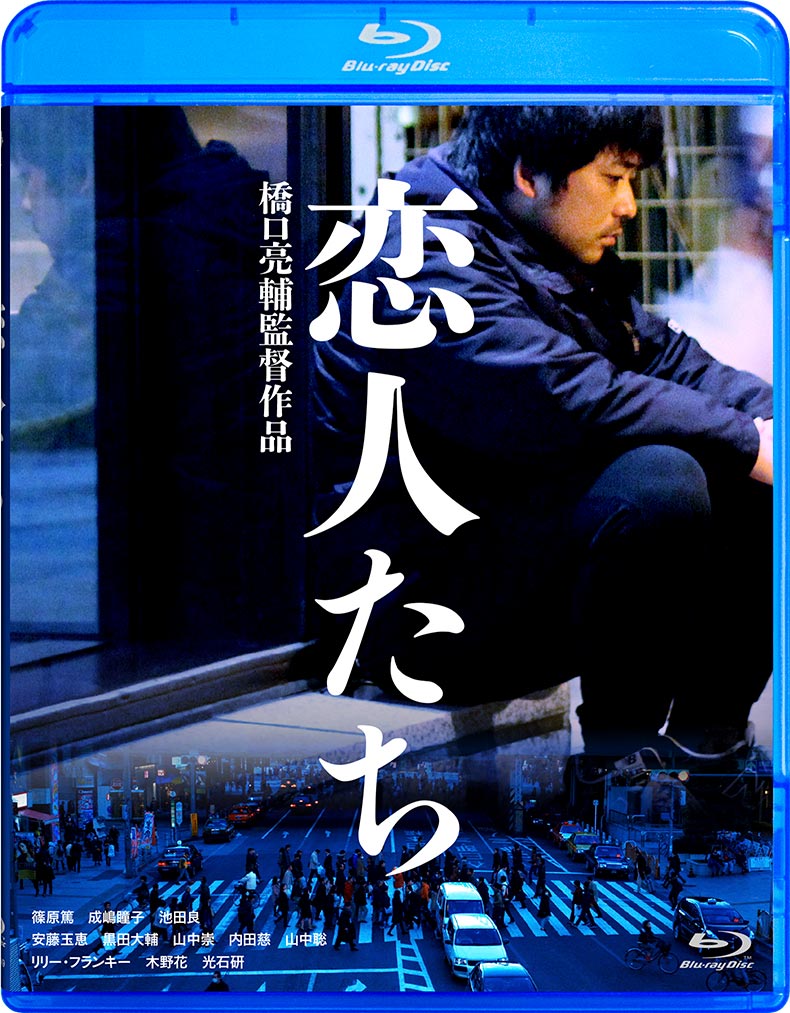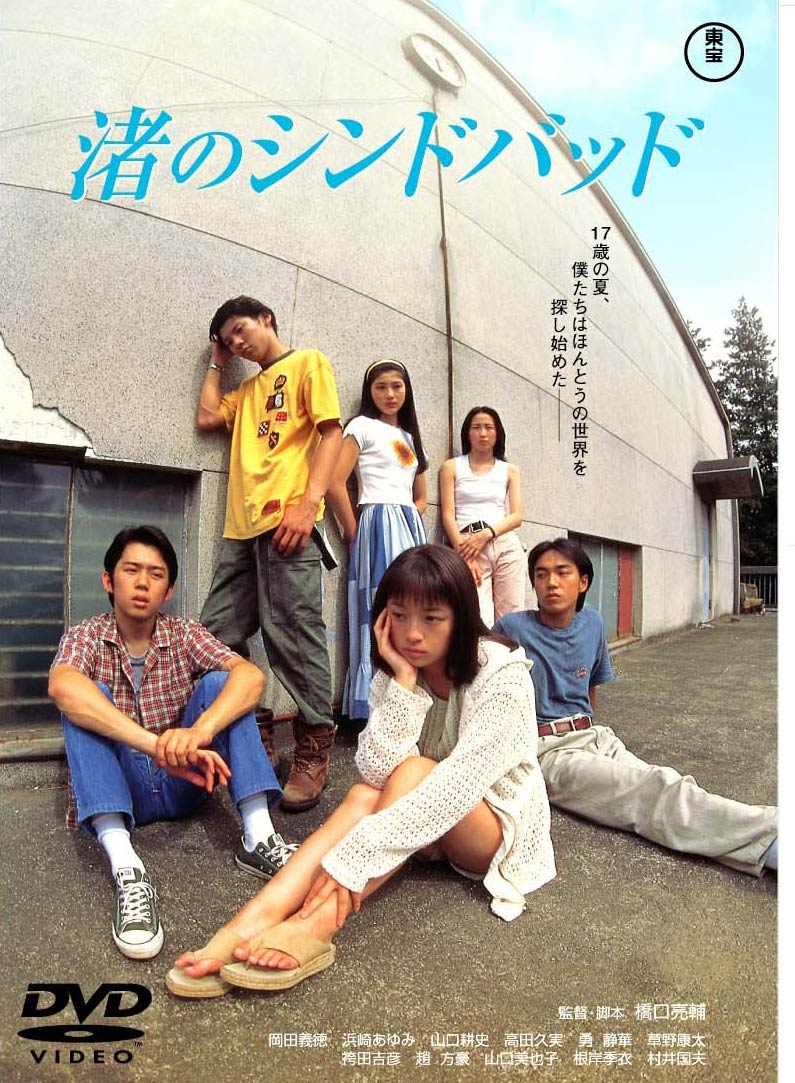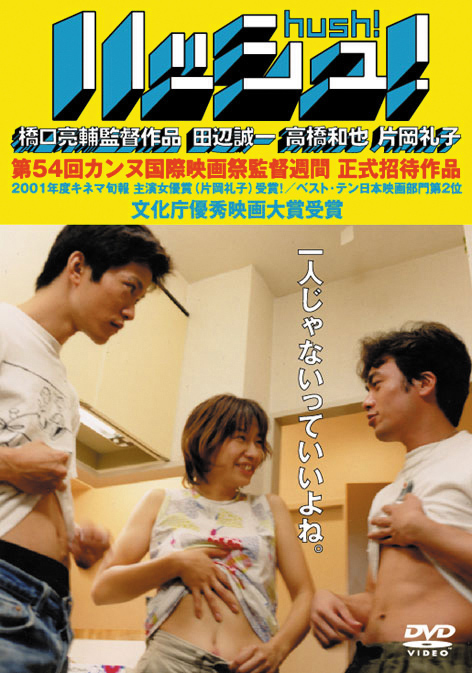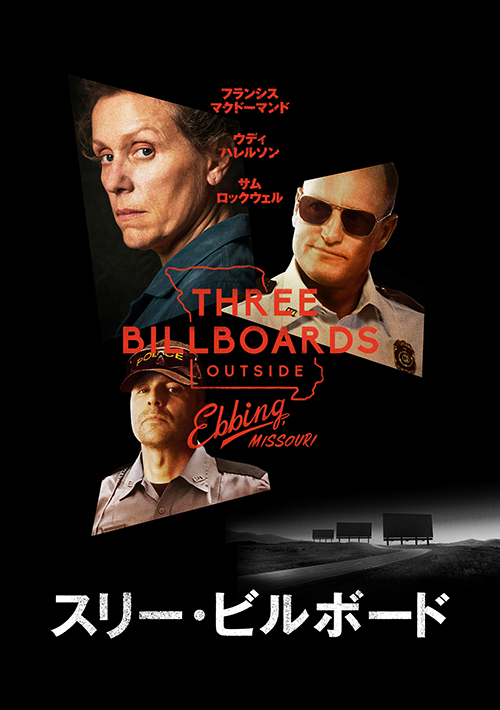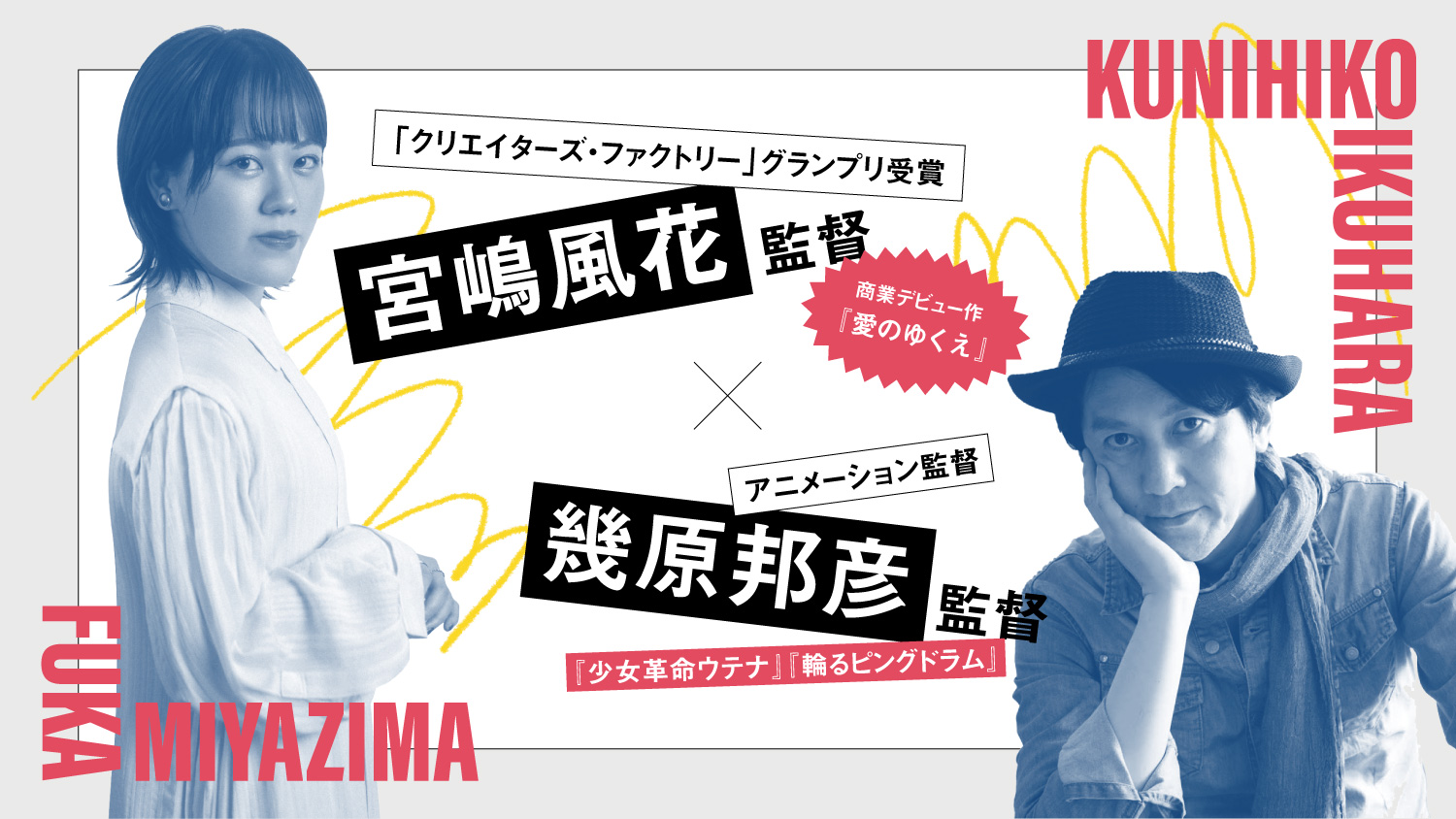目次

つくってみて、世に出して
初めて「ものづくり」への覚悟ができる
― お二人の出会いは、2015年に公開された橋口監督の『恋人たち』に野尻監督が助監督としては入られたことがきっかけ、ということですね。
野尻 : 実は、当時僕は40歳で、もういい歳だったから助監督はやりたくないと思っていたんです。
僕は、これまでなかなか“映画”を撮れなかった、というか撮らせてもらえなかったんですね。『鈴木家の嘘』を撮るまでにも、いくつか脚本を出してきたんですが、「お前の脚本は浮ついている」とか読んでもらった人に色々言われたんですよ。「浮ついてるってなんだよ」とか「面白ければいいんじゃないか」と思う一方で、「そうだよな」という想いもあって…。
― そんな中、橋口監督の『恋人たち』で助監督をしないかという話があったと。
野尻 : 橋口さんは、僕が学生の時にはすでに『二十才の微熱』(1993年)が話題になっていて、スター的な存在でした。でもかつての僕は、橋口さんのような…って言ったら失礼かもしれないけれど、自身の経験をもとに描いた映画ってどうなんだろうなって懐疑的な節もちょっとありまして…。
橋口 : と、さっそく若干のディスりが……傷ついた! 帰る!!(笑)

野尻 : いやいや、そういうことではないです…!(笑)
― (笑)。『二十才の微熱』は、第6回PFF(ぴあフィルムフェスティバル)スカラシップ作品として製作・公開された橋口監督の劇場用映画デビュー作ですね。主人公はアルバイトとしてゲイバーで身体を売る大学生で、橋口監督はご自身が同性愛者であることを公表されていました。
野尻 : でもその後に、橋口監督の『ハッシュ!』(2001年)を観てびっくりしたんです、「え、これが『二十才の微熱』と同じ監督!?」って。人間の底力とエンターテイメント性の凄さを目の当たりにして、とても驚きました。僕はそういう立場ではなかったですし、そういう方が周りにもいなかったにも関わらず、すごく感動したんです。「一体どうやったらこういうものが撮れるんだ?」と思いました。だから、橋口さんの現場だけはこの目で見て、「何をしているんだ?」ってことを全部盗んでやろうと。
橋口 : 『ハッシュ!』も言わば、「私(わたくし)」の映画だからね。
― 『ハッシュ!』はゲイのカップルと、一人の女性が新しい家族の形を模索する作品ですね。
野尻 : 僕の場合は、「これまでに自分が観てきた面白いものをつくりたい」という想いだけでここまできて、“オリジナリティがあるもの”をつくりたいということはあまり考えてきませんでした。
― 「自分が観てきた面白い」映画とは、どんな映画ですか?

野尻 : いや、もう恥ずかしい…いや、恥ずかしくはないんだけど(笑)。少年時代はやっぱりスピルバーグとかルーカスの作品を観ていましたね。あと、テレビで火曜から日曜まで映画を放送していたので、それを観ていました。クリント・イーストウッド、シュワルツェネッガーなどが出演している映画とか。あとは淀川長治さんが解説を務める『日曜洋画劇場』は確実に観ていました。
― 橋口監督は、どんな映画に影響された、などはありますか?
橋口 : うーん…、何かの影響と言われれば、『スター・ウォーズ』ですかね。ちょうど僕が中学二年生の時、1977年にアメリカで『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』が公開となって。で、SFが好きだったので自分でもつくってみたいと思って、8mmカメラを親にねだって撮り始めましたけどね。でも、「俺は映画監督になってやろう!」なんて気持ちは全くなかったですよ。
― そうなんですか?
橋口 : 親から「大学卒業したら絶対帰ってこい、なぜならお前は平凡な人間だから」って言われて、自分でもそうだと思っていたので普通に就職するんだろうなと思っていました。「ミュージシャンになりたい」「女優になりたい」って、どうやったらなれるか普通わかりませんよね。特に映画監督なんて「一体どうやってなるものなんだ…?」という感じでしょう?(笑) 偶然ですよ、人生なんて。
― (一同爆笑)

橋口 : はははは。『二十才の微熱』だってヒットしましたけど、デビューしたくてしたわけじゃないですからね。
野尻 : あ、そうなんですか?
橋口 : そうだよ! 「これを撮って、俺はこれでプロになってやるんだ!」なんて、全く思っていない。たまたまヒットして、「…どうしよう?」って感じですよね(笑)。そんなもんです、人生。自覚なんてね、本当に撮って初めて出てくるもの。
― 『二十才の微熱』を撮った後、何かご自身に変化があったということでしょうか。
橋口 : 僕の場合は、全国からいっぱいお手紙をいただいたんですよ。当時、同性愛を扱った映画は珍しかったですから。「橋口さんの映画を観て死ぬのをやめました」という15、16歳の方からの手紙だったり、「親に同性愛がばれて、もう死ぬしかないと思っていたけど、今は美容師を目指し頑張ってやっていこうと思っています」というものだったりを。あるいは、同性愛ということじゃなくても、ある女性の方から「私は人と違うんです。みんなと一緒にしなくちゃダメだと思っていたし、それが本当に辛かった。けれどこの映画を観て、私は私でいいんだと思いました」という手紙もいただきました。

橋口 : そういうメッセージをいただくと「ものをつくるって大変なことなんだな」っていうのがわかる。何かを発表するということは、それに対するバッシングだって当然あるわけです。つまり「ものをつくって出す」ということが「人を救うことも、人を殺すこともある」という重さを持っていることに、取り組んでみて初めて気づくんですよ。だから「映画をつくってお金をいただくっていう仕事をしよう」と僕が思ったのは『二十才の微熱』以降のことになります。
― つくったあと反応を受けて初めて、「ものづくり」に対する覚悟ができたんですね。
橋口 : そうやって、つくることを始めて「自分にしかできないことって、何だろうな」って考え始めると、自分と向き合わざるを得ないですよね。自分と、壁とにらめっこするみたいに向き合って、モノをつくっていると、自分の中にいろんなものが眠っていて「あ、俺ってこうなんだ」という発見がある。
そういうことと付き合って、長い時間をかけ「ああでもないこうでもない」と磨いていく。すると、それが結果、個性になるんです。そうして作品をつくっていくと、“わかった”ことと、“わからない”ことがまた出てくる。「では、次はこれをつくってみよう」、それがものをつくる確かな根拠になるんです。

「自分は何を伝えたいのか?」「どうすれば伝わるのか?」
“共感”は、その先に生まれる
― 野尻監督は『鈴木家の嘘』を撮るにあたり、「『家族』とは何か、知りたくてこの脚本を書いた。『家族』とは何か、あまり考えたことがなかった。」と、綴られていました。ご自身のお兄様が自死された体験を元に、この映画をつくられたわけですが、その辛い体験を題材に選ばれることに迷いはなかったのでしょうか。
野尻 : 橋口監督が言うところの、“根拠”を僕はずっと探していたと思うんですよ。僕は、橋口さんとは逆で、それがずっと見つからなかった。漠然と「映画監督は、楽しい仕事だ」みたいな気持ちがあっただけで、自分の内面を見つめることはなかったんです。じゃあ、自分が覚悟を持てることなんだろうって考えると…。
― “家族”のことが思い浮かんだ、と。
野尻 : 自分は兄の自死ということを体験した。正直に言えば、そういう事実を隠した時期もありました。だからそれを映画にするかどうかは、かなり悩みました。
― お兄様のことは、何年も誰にも明かさず家族の中で封印してきたとお伺いしました。そういうことに向き合うことは怖くなかったのでしょうか。

野尻 : 正直怖かったです。でも避けてはいけないと思いました。兄の死から全てが始まったので。なぜ、彼がそうしたかが僕なりの理解はあるのですがやはり、わからない。答えは出ないんです。でもしっかりと彼のことを考えて理解しようとしない限りこの映画を撮ってはいけないと思いました。
脚本を書くことが辛くて時には非常に難しかった。何度も形を変えようと思いましたが、逃げてはいけないと思い書き上げました。だから、本当にまだまだいろんな気持ちが混ざっているんだけど、自分が「嘘はつけないこと=自分の家族のこと」を一度書いてみて、そこから考えてみようかって。それで初めて自分の中にあるものに気づき始めた感じです。
橋口 : 『鈴木家の嘘』を観て、僕は彼がご家族のことで辛い体験をしたっていうことの中に、自分の役目というか、家族としてやらなきゃいけないんじゃないだろうかっていう想いを感じ、根拠がしっかりとあると思いました。完璧な作品とは、思いませんよ?
野尻 : ええー!
橋口 : 当たり前じゃん、何言ってんの? お前完璧だと思ってたのか、ばかやろう(笑)。…でも、不完全とも思いません。そういう、根拠がある作品っていうのは胸を掴む瞬間があります。同時に、そういう瞬間がある作品っていうのは貴重です。「自分が何を伝えたいんだろう?」「どうすれば伝わるんだろう?」ということを考えてない作品が多い。でも、野尻さんは「俺はこれを伝えたい」というのがちゃんとある人なんです。だから、この作品について僕は胸をつかまれる瞬間が何度もあったし、「ああ、よかったなあ」と思いました。

野尻 : 最初にも言ったように、「そんなに根拠のあるものをみんな観たいのかな?」って思っている部分も正直ありました。でも僕は、橋口さんご自身のことは詳しく知らなかったにも関わらず、『ハッシュ!』を観て、ものすごく感動した。それは監督の作業としては、とても大変なはずなんです。
橋口 : 野尻さんの、その気持ちはわかりますよ。たとえば小説家などでも自身の実体験を赤裸々に綴るっていうのは女性作家が多いでしょう? 映画もそうで、女性監督は自分のことを根拠に描けることが多い。でもそういう“自分の生々しいこと”を綴ることに対しての男性の拒否反応ってあるんですよ。当時、僕が自主映画をつくったときもデビューしてからも、「男性監督が自分のことを語る」ことに対して“女々しい”っていうような風潮はありました。野尻さんもそれと似た様なものを感じていたのではないでしょうかね?
野尻 : 男性のほうがどこかで自惚れていて「自分のことを、語らなくてもわかってくれるだろう」っていう想いが強い、というのもありそうですね。
橋口 : 履歴書やオーディションのプロフィール欄とかは如実です。女性はそういう時、自分のこといっぱい書くけれど、男性の場合は真っ白。女性のように「私(わたくし)を語る」ってことが苦手な男性は多いですよね。
ただね“私”って今言いましたけれど、同じ“私”でも、それが内に閉じていたら観客に伝わらないわけです。映画でも小説でも“私”を多くの人に伝えないとならないわけですよ。肉親を亡くした悲しみなど、そういった痛烈な体験をより多くの方に共有してもらうというのは、普遍にしていくという作業・表現なんです。

絶望を描いてもいい。でも観た人を絶望させてはいけない
― 野尻監督は『鈴木家の嘘』脚本執筆の際、橋口監督に相談されたそうですね。
野尻 : この脚本を書いている時に、橋口さんに「僕も今、自分のことを脚本として書いています。橋口さんのようにちゃんと広がりのある映画にしたいんですけど、どうしたらいいでしょうか?」という相談をさせてもらいました。その際、先ほどもお話しされたように「閉じた世界ではだめだ、ちゃんと自分のことを普遍性があるように切り取らなければ映画は伝わらないよ」とアドバイスを受けました。
― 普遍性、ですか。
野尻 : この脚本をプロデューサーに持って行った時、「この脚本は野尻さんの家族の話だが、私たちの家族の話でもある。」と言ってくださいました。それと同じで、僕は『ハッシュ!』を観る以前は出てくる人間は特殊で、僕とは違う人間だと思い込んでいました。だけど観て感動したのは、自分と同じ人間がいると思ったんです。ものすごく普遍性があるっていうことなんです。

橋口 : アカデミー賞をたくさん受賞した『スリー・ビルボード』(2017)って映画があります。この作品は、アメリカの中西部の片田舎に住む娘を殺された名も無い母親が主人公です。犯人は逮捕されず警察も動かない中で、母親自らが看板を出しそれが波紋を起こす、というお話。僕はこの映画を観たときに、あの母親の必死にもがいている姿を、我がことのように感じました。映画を観ながら拳に力を入れてしまったり、歯を食いしばったり、涙を流したり。まるであの母親を知っている人のように感じ、そして物語そのものに飲み込まれてしまうような感覚を受けたんです。
― 行ったこともない国の、知らない人に、なぜだか私たちは感情移入しているわけですね。
橋口 : それは、まさに「今」を描いているからなんです。「アメリカの今」ではなく、「世界の今」を描いているから。あの作品にはトランプ大統領もセクハラ問題も、“今のニュース”は何も描かれていません。名もない田舎のおばさんが頑張っているだけなのに、私たちと“同じ”であると感じる。「ああ、今、世界はこうなんだ」というのが私たちには伝わるんです。「僕たちが抱えている感情で、これは今の世界のありようなんだ」って。
つまりそれは「普遍が描けている」ってことだと思います。「今を描く」っていうことが、「普遍を描く」ということと全く同じなんだ、ということが『スリー・ビルボード』では端的によくわかり、僕はそこに感動しました。

― 橋口監督は『二十才の微熱』『渚のシンドバッド』(1995年)『ハッシュ!』と、同性愛を題材に3本作品をつくられました。先ほどもおっしゃられていたように“私”を描いているからこそ、誰にでも伝わるような映画にするために苦心されたのではないでしょうか?
橋口 : 当時から「なんだよ、オカマの映画かよ」って散々言われました。だから、それを“どう普遍にしていくか”“どう伝えていくか”については、今以上に気を配り、腐心したと思っています。だってね「俺はこう思う。それをわからないほうが悪いんだ」という描き方をしても誰も観てくれないし共感もしてくれない。
やっぱり「これは、あなたたちが生きている、今、この世界の話なんだ」っていう、その関係を説得しないといけない。
― 野尻監督にも、その「自分が生きている世界」と『鈴木家の嘘』の関係性が伝わるように、というアドバイスをされたということですね。
橋口 : そうするとね、日本の名も無い一家族の“鈴木家”の話であっても、同世代だけでなくいろいろな世代の人、あるいは映画祭で世界の人たちに「こういうことあるな、人間って」と思ってもらえる。たとえストーリーとして現代的な風俗を描いていたとしても、根本で“人間の普遍的な感情”をしっかりと押さえておけば、時代を超え、国を超えて変わらない「人間」が描けるんです。そうすれば、海外に持って行った時にも観客に伝わるし、時代も超えていく。「人間の姿」をそこに描いていれば「映画は確かなものになる」と、僕はそう思います。

野尻 : 『鈴木家の嘘』でいうと、兄が自死をするというのは、少し特殊で、世の中に多くあるようなことではないかもしれません。でも、大事な人を亡くした時の、自分の気持ち、そして父や母の気持ちは普遍的なものだろうと。あと、僕はやっぱり「笑える映画」が好きなので。深刻な時ほど笑ってしまいたいなって思います。
― 『鈴木家の嘘』では、悲しみを乗り越えるために、母親に対して「兄は生きている」という“嘘”をつきますね。肉親の自死というシリアスな題材を扱っていながらも、何度も思わず笑ってしまいました。
野尻 : 深刻であればあるほど、人の行動って、自分では真面目にやっているはずなのに他人から見るとおかしく見える。そういう部分をちゃんと切り取れば、生命力のある人間が写し取れるなと。それが結果笑えなくても、人間の生命力が写っているものになるだろうとは思っていたので。“あえて笑わせよう”というよりは、人間をまっすぐに描けばそこに通じるかな、と。
橋口 : 若い役者さんもそうですけど、「泣く」などのシリアスな演技はみんなできるんです。でも、「笑い」はハードルが高い。悲惨なことを明るく語ってみせたり、そこに希望を見出したりっていうのは“つくり手の力”だと思います。だから日本で今、コメディに特化されている矢口史靖監督や沖田修一監督のことを、僕は尊敬しています。一番ハードルの高いことに特化して挑戦され続けているわけですから。『鈴木家の嘘』のように、シリアスに語ることができるはずのことをコメディで描くということは、つくり手としての野尻さんの資質なんだと思いますよ。

― 『鈴木家の嘘』という映画をつくったあと、「家族」とは何か、答えは出ましたか?
野尻 : 家族のことがよくわからなくて、それを探すために書いた脚本でもありました。映画を撮れば答えが見つかるかなと思っていたのですけど、なかなか見つからず…。まあ……ひとつだけ思ったのは、背負って生きていくしかないんだなということ。
― “覚悟”ができたということでしょうか?
野尻 : 覚悟というか、「受け入れる」ということですかね。頭で考えすぎないでいい、ちょっと重たくなるぐらいだよね、と。
橋口 : 映画は「絶望を描いてもいい」けれど、それを観た人を「絶望させてはいけない」と僕は思うんです。フランソワ・トリュフォー監督も「私たちは混沌とした世界を生きていて、映画というのはその混沌の中に道筋をつけていくものなんだ」ということを言っています。
― 混沌とした世界に道筋をつけていくのが、映画だと。
橋口 : 映画って、いかにも現実をそのまま切り取っているかのようにみえるけれど、実際は現実をすり寄せながら、世の中に存在するいろいろな問題に対してストーリーをつくり、そこに道筋をつけ、登場人物に何かを託していくことです。

橋口 : だからこそ、映画は決して、絶望や混乱をそのまま観客に手渡してはいけないと思います。もちろん、つくり手ごとにいろいろと狙いがあるんだろうとは思うし、「必ず希望を描け」とは言わない。けれど、観客にとっての“出口”がどこかに無いと、やっぱり表現としてはだめなんじゃないかって僕は思いますよ。
野尻 : 今まで家族の存在ってものを否定していた部分が大きかった。でも否定とか肯定とかではないんだなと。これはもう、体に生えたコブのようにとれないもの、全部受け入れていくしかないんだろうな、と今は思っています。
なんでしょうね、家族って。家族を厄介なものだと思っている人も多いと思う。この映画を観て思うところは人それぞれでしょうけど、前向きになってくれる方もいるのではないかな、と。”厄介”って、マイナスに聞こえるかもしれないけど、僕にとってはそう思えるだけでも実は結構前向きな気分なんです。
― 父親役を演じた岸部一徳さんも、「ラストに向かって前を向いて生きていく気持ちで僕らも演じたので、観る人にもその光を感じてもらえればと思います」とおっしゃっていましたね。
野尻 : 「映画」には答えがないように、「家族」にも答えはない。でも、答えを知りたくてもがいてしまう。だからこそ、家族は映画になるのだと思いますね。

- 自分を閉ざさなければ、 「光」は見える。 暗闇の中でも
- ものとして、記憶として、 残り続けるポスターやパンフレットをつくるために
- 「グッモー!」と「サンキュー!」の気持ちがあれば。僕を育てた渋谷と映画【後編】
- 「グッモー!」と「サンキュー!」の気持ちがあれば。僕を育てた渋谷と映画【前編】
- 映画が「好き」だから、「本気」で観る。古今東西の作品から受け取ったもの
- 映画と出会う場をつくり続けてきた土肥さんに聞きました。「映画だから、できることって何ですか?」 【後編】
- 映画と出会う場をつくり続けてきた土肥さんに聞きました。「映画だから、できることって何ですか?」 【前編】
- 映画好きなら誰もが一度は触れている、大島依提亜さんのデザインの秘密にせまる! 宝物のようにとっておきたくなるポスター・パンフレットとは?
- まるで寅さんのように。 「フジロック」≒『男はつらいよ』!? 時代を切り拓く男の共通点
- わたしのすべては映画でできている。 6歳で“映画音楽作曲家”を志した彼女の美学
- 「その痛みを想像できるのか?」 死ぬこと、殺すこと、生きること。
- 「会社を辞めて、生きていけるワケがない!」その“呪い”から、映画と旅が解放してくれた
- 「ものをつくって世に出す」ということは、人を救うことも、殺すこともある。“ものづくり”の本質とは?
- 「スピルバーグにできて、自分たちにできないはずはない!」 大友啓史監督の創作の秘策とは?
- 世界的タップダンサー熊谷和徳の道は、1本の映画から始まった【後編】
- 世界的タップダンサー熊谷和徳の道は、1本の映画から始まった【前編】
- 「好き」と「かっこいい」を突き通す。いのうえひでのりの創造の原点となった映画たち【後編】
- 「好き」と「かっこいい」を突き通す。いのうえひでのりの創造の原点となった映画たち【前編】
- 人生は矛盾だらけ。そこを乗り越えようと「もがく人」は、魅力的だ