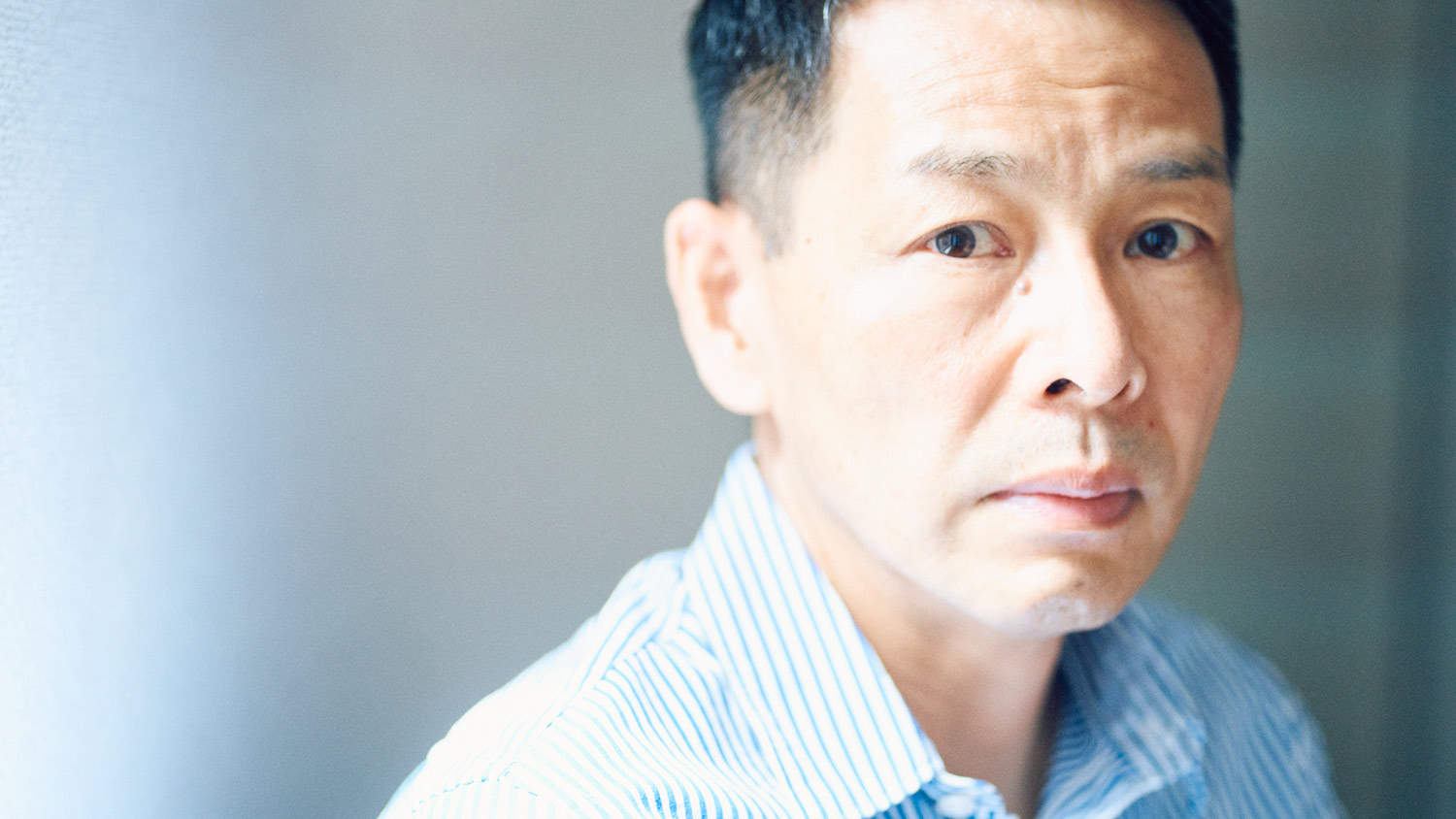目次

一冊の本や紙芝居を編集するように
― サンフランシスコ湾に突き出したダイナーで朝7時のオープンに向けて準備をするウェイター、日曜日のシギリアで夜行列車に乗り込む人々、マルセイユの夜道を走らせるタクシー運転手、台南の海近くで早朝牡蠣を剥く女性たち、メルボルンの街を毎晩歩き続ける男性。本作では、「早朝」と「深夜」の人の営みが記録されていました。松浦さんは自身が旅するときも、「出かけるのは早朝と夜ばかりだ」とおっしゃっていますが、それはなぜでしょう?
松浦 : 長年自分が旅をし続けてきて、昼間というのは、人の暮らしがセットアップされちゃっているな、と感じていたんです。
― だいたい同じような人の動きになっている、ということでしょうか。
松浦 : 情報が多すぎてわかりづらいといいますか、僕個人としては、美しい光景にはなかなか出会えないところがあって。ある時から、旅先では、季節にもよりますけど日が昇る4時とか5時とか、深夜に出かけるようになりました。
まだ人が起き始めた頃って、街が動き始める時間帯なんですよね。そこには、家の窓を開ける人がいたり、朝食を作る人がいたり、これから一日を始める人たちの営みがある。それが、僕にとってはすごくハッとするような、それまでの旅では出会えなかった光景だったんです。

― 日中のにぎやかさとはまた違う、静かな営みが浮かび上がってくる時間帯だったと。
松浦 : 深夜も同じように、みんなが寝静まっている中で働いている人がいたり、家の中で小さな灯りをつけて本を読んでいる人がいたり。その静けさも、僕は暮らしそのものだと思うし、僕にとっては、暗闇の中で明かりが灯るような美しさなんですね。
日中の楽しさもあるけれど、僕は早朝や深夜の街の光がすごくきれいだと思うんです。旅をする中で、日常というのは多くの人が活動している昼間だけではないということに気がつきました。
― 今作は、世界5カ国・6都市の現地の人の営みが記録されています。各都市に一週間程滞在して、早朝の5〜8時、 深夜の24〜26時に撮影をするスタイルだったそうですが、それは松浦さんがこれまでの旅で見つけた「人の姿を見つめる視点」を反映しているんですね。

松浦 : 大げさに言うと、例えば人の暮らしに「陽」と「陰」があるとすれば、いつも「陽」の部分だけが表現されている気がしていたんです。でも、「陰」の部分にも命の営みがある。そうしたひとつの眼差しを、映画というかたちで記録ができたらいいなと思いました。
撮影も、一日の予定をきっちり決めて行うわけではなく、その日、その時の状況をそのまま記録したものなんです。出会った人たちに少しお話を伺ったりもしましたけど、インタビューが目的ではなく、旅先にあるなんでもない光景を、6つの都市で記録したいなと思って撮った作品です。特別なことは何も起きないし、答えが用意されているわけでもない。問いかけに近いような、コミュニケーションのような映画なのかなと。
― 今作のプロデューサー石原弘之さんは、エッセイストや編集者、書店オーナーとして著名な松浦さんに、あえて監督のオファーをしたとプロダクションノートに綴られていました。
松浦 : 僕は映画監督としてのキャリアがあるわけでもないので、いわゆる本来の「映画作り」はできない。できるとしたら、紙芝居や、ひとつの読み聞かせ絵本のような作品にすることかなと思ったんです。

松浦 : なんでもない光景を切り取り、自分たちの感情的な部分は、できるだけ排除しようと思って編集していました。
― それは、どうしてですか?
松浦 : 何かしらの出来事に出くわすと、僕らは感情が動くと思うんです。思い入れが強くなったり、形に残したいと思ったり。でも、答えを言ってしまうようなことは逆にしたくなかったんです。感情よりも、なんでもない光景の方がすごく大事だなと思いましたし。
僕は編集者なので、マクロ的に全てをマネージメントする気はあまりありませんでした。たくさんの素材を記録してもらって、それをどう紙芝居にしていくのか。カメラマンやプロデューサー、音響スタッフなど、この映画に関わってくれた人たちの個性や視線、気づきをどれだけ活かしていくかということを意識していました。
― 映画を作るということは初めての経験でも、松浦さんが長年積み重ねてこられた編集者というお仕事と、共通する部分があったと。
松浦 : 近かったです。もちろん、落とし所は映画なんですけど、6つの都市で撮ろうということ以外、脚本があるわけではなかったので、どんな作品になるのか、最後までわからない状況だったんです。そうなると、どうしても僕は編集者なので、映像なんだけど、一冊の本を作るというような感覚に近くなっていましたね。

世界が変わっても、
人間の営みの本質は変わらない
― この映画は2019年の5月から7月に撮影され、完成したのは2020年の2月と、まさにコロナ禍に差し掛かるような時期でした。撮影中と現在では世界が一変してしまい、今作に映し出された何気ない光景も、今見るとどこか懐かしい気持ちになります。
松浦 : どうしても、コロナのことでノスタルジックに感じてしまうところはありますね。でも、それだけじゃないなとも思います。どこの国でも、どこの街でも、人が一生懸命に生きていることは変わらない。コロナで世界が変わっても、日々暮らしに向き合って、歯を食いしばって生きているということは、一緒なんだなと感じました。
― コロナで失われてしまったものよりも、世界が一変しても変わらないものが浮かび上がって見えたのですね。
松浦 : はい。旅をテーマにした映画なので、旅の楽しさをイメージしてもらっても嬉しいんだけど、それよりも、人が生きていることの愛おしさ、みたいなことの方が僕は大切な気がします。

― 今作では、「自分らしい呼吸を取り戻す時間」として「旅」が描かれていますが、旅に出ることが難しくなってしまった今、限られた行動範囲の中で過ごすことに、誰もが息苦しさを感じているような気がします。松浦さんは、旅に出られなくなってしまった代わりに、大切にしていることはありますか?
松浦 : 旅に出られなくなって、もう2年位経ちましたけど、みんなその代わりになるものを探しているな、というのを感じますよね。旅というのは、自分自身に立ち返ったり、気分をリセットするものでもあったけど、その代わりは、なかなか見つけられないとも思います。何か解決する方法があるだろう、と最初は思っていましたけど、実際はそう簡単でもなくて…僕自身もまだ見つけられていないんです。
― 一方で、家で過ごす時間が増えて、みんなが一斉に、自分の暮らしに向き合う機会にもなりましたよね。松浦さんは、『暮しの手帖』や、ウェブメディア『くらしのきほん』の運営など、生活や暮らしということを軸に活動されてきましたが、コロナ禍で暮らしが一変してしまった今の状況を、どのように感じていますか?
松浦 : 外食ができないと自分で作るし、家にいる時間が長いので、家で何とか楽しみを見つけてみようとしますよね。でも、まだみんなの中に、戸惑いは残っているんじゃないかという気がします。僕も、こうすれば楽しくなるよ、という方法はいろいろあるんですが、戸惑っている気がしますし、まだ「新しい暮らし方」というものは見つけられていなくて。

松浦 : 僕自身が発信しているものも含めて、いろいろなメディアで解決策のような方法は投げかけていますけど、これから先、どうやって不安なく心地よく生きていったらいいのかは、誰しもが不安なんじゃないですかね。根本的な解決は、まだ誰もできていないんじゃないかな。
― 今作の冒頭で「人間が人間らしさを失わずに、どうやってその生命を享受するのか」という言葉がありましたが、まさに今、変化した世界で皆がそれを模索している段階にありますね。
松浦 : 解決策が見つかってないとはいえ、前向きに生きていきたいので、しばらく模索しながらも、だんだんと自分らしさを取り戻していくしかないし、それでいいのではないのかなと。簡単に解決できなくてもいいのかなと思っています。

松浦弥太郎の「心の一本」の映画
― 旅に出られない日常の中でも、自分にゆっくりと向き合ったり、遠くに出かけたような気持ちを味わうことができたりするのが、映画の醍醐味のひとつだと思います。松浦さんは、映画をよくご覧になりますか?
松浦 : 人並みですけど、子どもの頃から思春期を含めて、いろんな映画を観てきました。本と映画と音楽というのは、昔から自分にとって、何かを感じさせてくれたり、教えてくれたりするような存在でしたね。
― どのような映画がお好きですか?
松浦 : 子どもの頃は、アクション映画とか、いわゆる娯楽作品が好きでした。そこを入口として、20歳くらいになると、ヨーロッパの映画を観るようにもなりました。「映画って芸術性が高いな」と思ったり。刺激の強いものは苦手かもしれませんね。音楽や音が衝撃的に用いられているとか…(笑)。そういう映画よりも、静かな淡々とした映画のほうが好きです。
― 今作『場所はいつも旅先だった』のように、生活音が響くような作品がお好きなのでしょうか。

松浦 : そうですね。映画作りに携わって思ったのは、音響って、映像と同じくらい映画の要素として大事なんだなということです。僕自身、音楽は静かなものを好んで選ぶことが多いですし。
あとは、答えがはっきりとわかる、起承転結がある作品よりも、いつまでも静かに余韻が残るような映画が好きです。しばらくその映画について考えたり、ふとしたシーンを思い出したりするような。
― 観た後、静かに余韻が残るような映画として、思い浮かぶ作品はありますか?
松浦 : 断片的なシーンをふと思い出すのは、『情事』(1960)という、イタリアの古い映画です。人から好きな映画を聞かれると、いつも思い浮かぶんです。
― ミケランジェロ・アントニオーニ監督の作品ですね。旅先の地中海でアンナ(レア・マッサリ)が姿を消し、残された恋人のサンドロ(ガブリエル・フェルゼッティ)とアンナの親友・クラウディア(モニカ・ヴィッティ)が行方を探すうちに、親密になっていくというストーリーです。失踪したアンナも最後まで見つかることはなく、作品全体に不思議な空虚感が漂う映画です。
松浦 : なぜかは説明できないんですけど、作品の中のふとした光景をいくつか思い出すんですよね。
― それは、どういうシーンでしょう?
松浦 : ラストシーンに近いところで、クラウディアを裏切ってしまったサンドロが佇んでいて、やってきたクラウディアが言葉なく、ただ彼の肩に手を置くんです。そういうなんでもないシーンなんですけど、「あれが意味するのはどういうことだったんだろう」って、自分の中で考え続けているんです。何度も観ていますけど、未だに余韻が残る映画ですね。
― 以前、行定勲監督にインタビューした時も、お好きな恋愛映画として『情事』を選ばれていて、同じラストシーンのことをお話ししてくれました。
― 松浦さんは、好きな映画の話を誰かとされたり、気になったシーンを考察したりはしますか?
松浦 : この話は、今初めてしました(笑)。仕事でも、映画について聞かれたり話したりする機会があまりなくて。だからなのかはわかりませんが、心の中でずっと消化されていないんですよね。魅力的というか、あの世界観が好きなんだろうなと思います。
「人と出会う」ということにおいても、そういうことってありませんか? すぐ忘れちゃう人もいれば、ずーっと覚えている人やふと何度も思い出す人もいる。なんであの人のことを思い出すのかなって。それと同じなんでしょうね。
― 松浦さんの人生の傍らにいる映画なんですね。その余韻や問いに答えを求めているわけではなくて、ただ心に残っているという。
松浦 : そうそう、そうです。謎がいっぱい残る映画なんです。結構衝撃的ですよ(笑)。こうやって時代が変わっても、自分の心の中に残り続けている映画ってすごいなと思いますね。観る度に発見があるし。僕も、自分が作った映画がそうであってほしい。観る人それぞれに答えを委ねたいなと思っているんです。

↓『場所はいつも旅先だった』を読む!