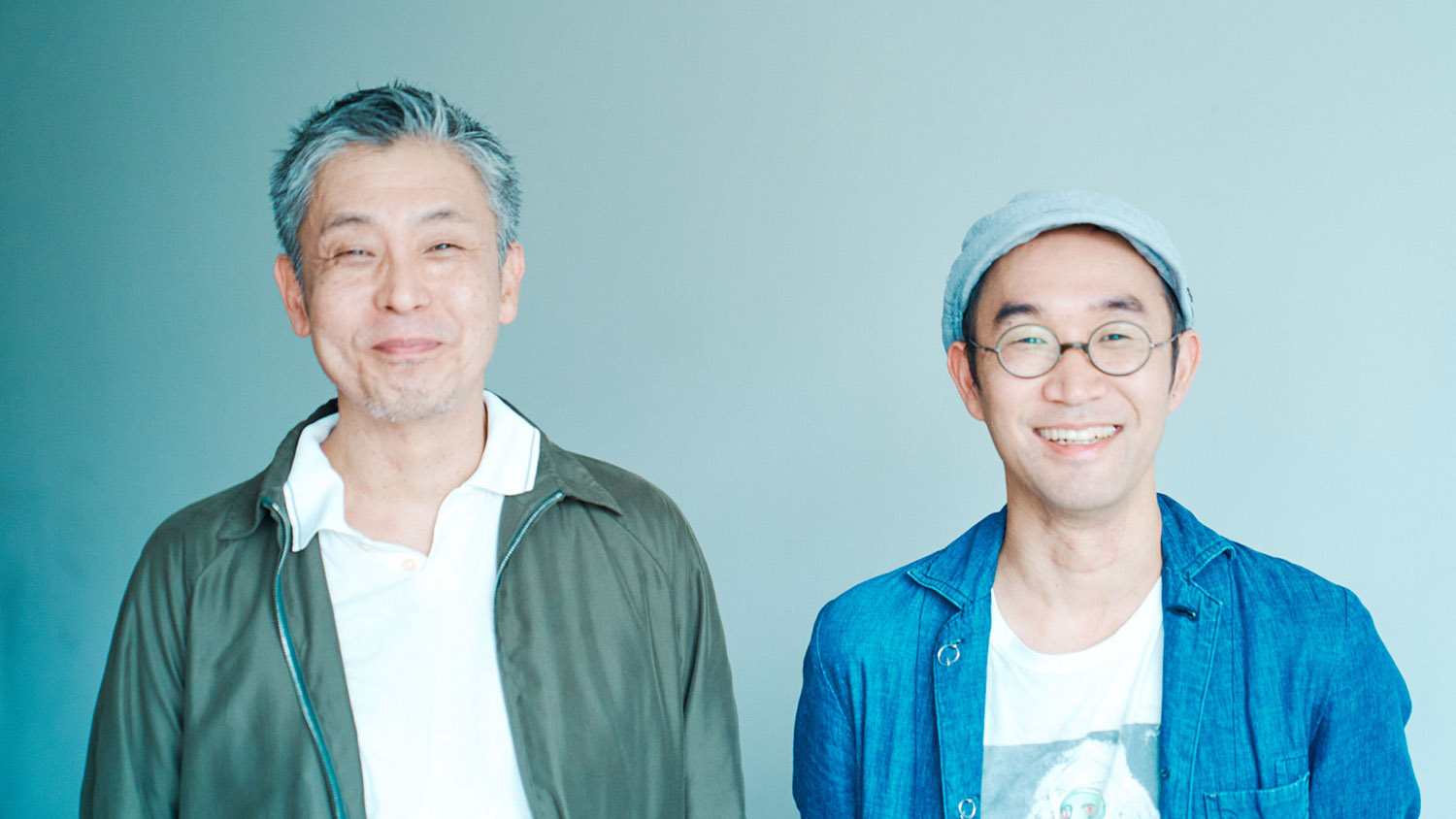目次
先人の言うことはあてにしなくていい!
― 作品を世に出してからは、いかがでしょうか? 今は視聴者や観客の反応がすぐにわかりますよね。
幾原 : 僕が最初にアニメを作っていた頃は、視聴者の反応はよくわかりませんでした。視聴率で数字としてしか見えない。でも、インターネットの登場で、今はダイレクトに反応がわかるから作り手の感性もガラッと変わったと思います。
― やはり、SNSでの反応は気にしますか?
幾原 : そこと距離を取りたいとは思うのですが、バランスが難しいです。そろそろSNSからは身を引くべきか…とも思うのですが。

宮嶋 : 私もエゴサはします(笑)。まだ批判的な意見に傷ついたことはないですが、俳優さんの中には絶対に見ないという方もいらっしゃいますね。
幾原 : 批判的な意見を見たときやバッシングを受けたときは凹みますし、大変な時代になったと思います。
ただ、強い支持は強い批判とセットだとも思っているので、強く批判されているということは、それだけ作品の力があったということだとも思っています。慣れないですけどね(笑)。そういう言葉に対する耐性も若い人の方があるんじゃないかと思います。
― 幾原監督から見て、やはり宮嶋監督のような若い世代と自分たちの世代とのメディアの向き合い方や創作の違いは強く感じますか?
幾原 : 全然違います! インターネットがこの世に出てきてから大体30年くらいで、宮嶋監督はデジタルネイティブといえる世代ですよね。


宮嶋 : SNSは高校に入学した頃から始めて、卒業する頃にスマホを持ち始めていたという感じでした。
幾原 : もうその時点で、生活の中心がデジタルメディアになっているということなので、やはり世界の見え方が僕らとは確実に違うはずです。昔は世界で何か事件や紛争が起きても、報道の映像がテレビで流れるくらいで、遠い存在に感じました。
でも今は、ウクライナやイスラエルで1時間前に起こったことがすぐに入ってくるわけで、世界がずっと狭くなったと思います。狭すぎて怖い。メディアに対しても、僕らの世代はメディアに権威性を感じながら育ったけれど、宮嶋さんの世代から見たら全く違うでしょうし。
宮嶋 : テレビを持っていないという友達は多いですね。私も東京にいるときはほとんどテレビを見ませんし。ニュースを追っている人もいれば、まったく興味がないという人もいて、それぞれが全く違う方向に向かっているという印象はあります。

幾原 : 今、メディアは大きな転換期を迎えています。夏目漱石の『吾輩は猫である』って何部売れたかご存じですか? なんと、2000部ほどしか売れなかったんです。というのも、当時、小説は本ではなく新聞で読むものだったからです。
それが高度成長期に伴って一般にも本が広まり、そのうちテレビの時代になり。僕が子どもの頃は映像の希少性があったから、ドラマやアニメ番組を見ることが楽しみでした。
― はい。
幾原 : 録画ができるようになったときは興奮しました、「繰り返し見れる!」って。その後、DVDなどパッケージメディアが登場し、「やった!これでもう永久に劣化しない映像で、好きな映画が何度も見れる」となり、動画配信になった。
そしたら、今その感覚は失われて、映像についてタイムパフォーマンスを求めるような感覚が出てきています。「映画は2時間スマホが見れないし、タイパ悪い」…って、もう僕らが理解できる感性ではないですよね。

― 確かに映像を繰り返し見られることが貴重だった時代から考えると、「タイパの悪い作品」って考え方自体が信じられませんよね。
幾原 : 「見る側」の感性もすごい勢いで変化しているので、僕らがこれまで大切にしていたものが10年後に存在しているのかは全くわかりません。
こういうメディアの転換期に仕事ができた自分は運が良いと思いますけど、宮嶋監督はテレビ登場以来の最大の転換期のど真ん中にいるわけです。おそらく作品の作り方みたいなものが、僕らが考えているものとは違っていると思います。

幾原 : スマホでぱぱっとショートフィルムを作って、すぐに発表できたりとか、そういう軽やかさも僕の世代にはないものですし。
これからメディアをどう変えていくのかというのも、ネットネイティブの人たちが作っていくと思うんで、そこに、僕が参加できないっていうジレンマはありますよね。悔しさみたいなものは感じます。
― 幾原監督の作品を見て育った宮嶋監督の世代の人たちが、今後のメディアのあり方を決めていく期待と悔しさとを感じていると。
幾原 : すごく羨ましい。僕もそこにいたかったです。

― メディア転換期のど真ん中にいる世代として、今後はどのような作品を作りたいですか?
宮嶋 : 今までは過去に向かう作品を作ってきたので、これからは「いま」を描きたいと強く思っています。自分の背中を押してくれるような作品になったらいいなと。
幾原 : 例えば宮嶋監督の作品を見て、「これは商業的に乗りづらい作品だよね」という人もいるかもしれないですけど、それが的を射ているとも思わないんですよ。 「タイパが悪い」みたいなこと言う人がいっぱいいる世界で、そんな普通の理論で発言しても仕方がないですし。
だから正直、僕なんかのアドバイスとか、成功体験なんて、何の意味もないと思っています(笑)。宮嶋監督も、「今はアニメですよね」って言いだして今度はアニメーションをつくるかもしれませんし。宮嶋監督がこれからどんな作品をつくるのか、楽しみです。

宮嶋 : 私、『親知らず』をつくる前に、映画館のマナーCMを作ったことがあって、それが札幌の映画館で上映されたことがあったんです。生のお客さんの反応を見ることができたんですが、やっぱり作品は人に観てもらって完成するんだなと、その時の高揚感がずっと心の中にあります。
だから、卒業制作の『親知らず』もたくさんの人に観てもらいたいと思って応募しました。『愛のゆくえ』も、お客さんと一緒に映画館で体験したいという気持ちが強くあります。一人一人反応は違うと思うし、それを体感できることが今からとても楽しみです。

宮嶋風花と幾原邦彦の「心の一本」の映画
― 最後に、「心の一本」の映画を教えてください。お二人が創作する上で源泉になっているような、そんな映画はありますか?
幾原 : 好きな映画は常に変わるのですが、『愛のゆくえ』を観た今は、フェデリコ・フェリーニ監督作やNHKドラマ映画『四季〜ユートピアノ~』(1979)も思い浮かんだのですが、レオス・カラックス監督の『ポンヌフの恋人』(1991)を挙げようと思います。
― 『ポンヌフの恋人』はレオス・カラックス監督による1991年の作品で、ホームレスの青年と失明の危機に瀕した画学生の女性との恋を描いた作品です。
幾原 : 実物大の橋のセット、ビックリするようなスケールの大きな撮影、ラストシーン、全てが好きです。台本では悲劇的な終わりだったのを、ヒロイン役のジュリエット・ビノッシュが受け入れず、あのラストシーンになったという逸話も含めて好きですね。
― 宮嶋さんも特に好きな監督としてレオス・カラックス監督の名前を過去に挙げていらっしゃいました。
宮嶋 : はい。カラックス監督の作品には男女ふたりの出会いから別れまでを描く作品が多いですが、毎回ふたりとも社会のはみ出し者で、生きづらそうな感じがぶつかり合う。その感じが好きなんです。
― 『ポンヌフの恋人』もまさにそうですし、生きづらい男女がぶつかり合うという部分は『愛のゆくえ』にも通じると思います。

幾原 : ちなみに、僕には『愛のゆくえ』のふたりは男女のキャラクターに分かれたひとりの人物に見えたんです。片や東京に行った可能性であり、片や地元に残った可能性であり、最後にその片方ずつが一体になる……そんなイメージを持ちました。
― 宮嶋監督の心の一本はなんですか?
宮嶋 : 1本に絞れなかったので2本挙げたいんですが、1本目は七里圭監督の『眠り姫』(2007)です。
― 漫画家の山本直樹が内田百閒の短編小説「山高帽子」を基に描いた同名コミックを映画化した2007年の作品ですね。いくら眠っても寝不足を感じているヒロインが陥っていく夢と現実の境界のような世界観を表現しています。
宮嶋 : 人がほとんど出てこないのですが、その気配だけが感じられるという作品で、大学生のときに初めて観て衝撃を受けました。例えば電車の景色だったり、部屋の窓だったり、近所の猫だったり、 誰もいないカフェの店内だったりといったシーンで構成されていて、それとまた別に、記憶のシーンみたいな、夢の中のシーンがあって。
実験的な映画なんですが、なんだかすごく懐かしい気持ちになったんです。包まれているような気持ちになる作品です。
幾原 : DVD化されていないみたいですね。何とかして観てみます!
宮嶋 : そう言ってくださって、嬉しいです! 2本目はドン・ハーツフェルト監督の『ビルの物語』(2006)三部作です。
― ドン・ハーツフェルトは、一人で作画、撮影、編集をこなす個人制作スタイルの現代アメリカを代表するアニメーション作家です。
宮嶋 : 『ビルの物語』三部作は『きっと全て大丈夫』、『あなたは私の誇り』、『なんて素敵な日』というそれぞれ10分程度の短編で構成されています。大学の授業で観たんですが、キャラクターが棒人間なんです。ビルという棒人間が脳の病気を抱えていて、その頭の中を覗いているような感覚になる作品です。
頭の中を素直に表現しているというか、精神的に入り込んで体験できる感じがして好きなんです。映画じゃないと表現できない作品だなと思います。
― 2作品とも、かなり実験的な作品ですよね。
宮嶋 : はい。『眠り姫』も『ビルの物語』も、実験的で枠にはまらない映画ですが、私は普通では思いつかないような表現に挑戦しているものに強く心惹かれるという傾向があるんだと思います。
今回「心の一本」を考えてみて、私は見る人の頭の中に、いかにドンッと直観的に感じさせるかということにこだわっているんだと気づかされました。
幾原 : 僕は反対に、直観的にやっているように見せて緻密に考えてるタイプです(笑)。デジタルネイティブの宮嶋さんみたいにイメージの共有も軽やかにできないんです。
今は僕らの世代の人がまだいるからズレを感じることもあるかもしれないけれど、これからは宮嶋さんの世代の方がずっと軽やかにクリエイトしていくんだと思います。