
パリ。
数々の映画の舞台となっただけでなく、世界史に残る出来事の舞台ともなった都。
この街を舞台にした映画で、もっとも古い記憶として残っているのは、NHK教育テレビ(いまはEテレですね)で観た『巴里の空の下セーヌは流れる』。
1951年、名匠ジュリアン・デュヴィヴィエ監督による作品で、素晴らしい主題歌をエディット・ピアフが歌っていた。この作品のラストは衝撃的で、「名声」というものについてずいぶんと考えさせられた。
宮城県の片田舎でフランス映画に触れる機会は本当に限られていた。でも大学に入学するために上京すると、パリがグッと近づいた。早稲田松竹や高田馬場パール座、飯田橋の佳作座やらで、フランス映画との接点が増えたからだ。
1980年代後半、大学生の会話の中に「ヌーヴェル・ヴァーグ」(※)という単語がまだ飛び交っていた。監督で言うなら、ジャン=リュック・ゴダール、ルイ・マル、そしてフランソワ・トリュフォー。
実は、アメリカ贔屓の私からすれば、ヌーヴェル・ヴァーグの映画群は難解だったのだが、それでもトリュフォーの『アメリカの夜』、『アデルの恋の物語』、『隣の女』はとても気に入った。『アメリカの夜』のジャクリーン・ビセット、『アデル』のイザベル・アジャーニ、『隣の女』のファニー・アルダンと、それぞれタイプは違うが、トリュフォーが起用する女優にも魅せられた。
中でも『アデル』のイザベル・アジャーニは奇跡のような美しさを誇っていた。
トリュフォーの映画で、とりわけ印象に残っているのは、カトリーヌ・ドヌーヴ主演の『終電車』だ。時は第二次世界大戦中、ナチス占領下のパリ。緊迫した情勢の中でおりなされる、表現への葛藤と恋愛。
『終電車』を観た後、「自分はいつかパリに行くことがあるのだろうか?」と自問自答したことを覚えている。
大学生の私にとって、パリははるか遠くの異国だった。

初めてパリの土を踏んだのは、2007年のことである。ラグビー・ワールドカップのためにフランスを訪れた時だ。ロンドンから早朝のユーロスターに乗ってパリのGare du Nord、北駅へ。
最初に北駅のプラットホームを見た時の美しさは忘れがたい。改札の向こうに伸びるいくつかのホーム、クラシカルな天井。そこには“歴史”が感じられた。
その他に私が使ったことのあるパリのターミナル駅は、リヨン、そしてオステルリッツ。いずれも美しく、旅情を誘う場所だ。

ラグビー・ワールドカップの試合の合間、パリで、私の映画熱に火がついた。
1970年代にパリに留学していた先輩が、こうアドバイスしてくれた。
「生島君、パリに着いたら『パリスコープ』を買うように。まあ、『ぴあ』みたいなものです」
キオスクで『パリスコープ』を買い、映画名を赤ペンでチェックしていると、しびれるような感覚を味わった。
「パリは、東京よりも日本映画のクラシックが観られるじゃないか」
黒澤、小津、溝口、そして宮崎の名前がポンポン出てくる。
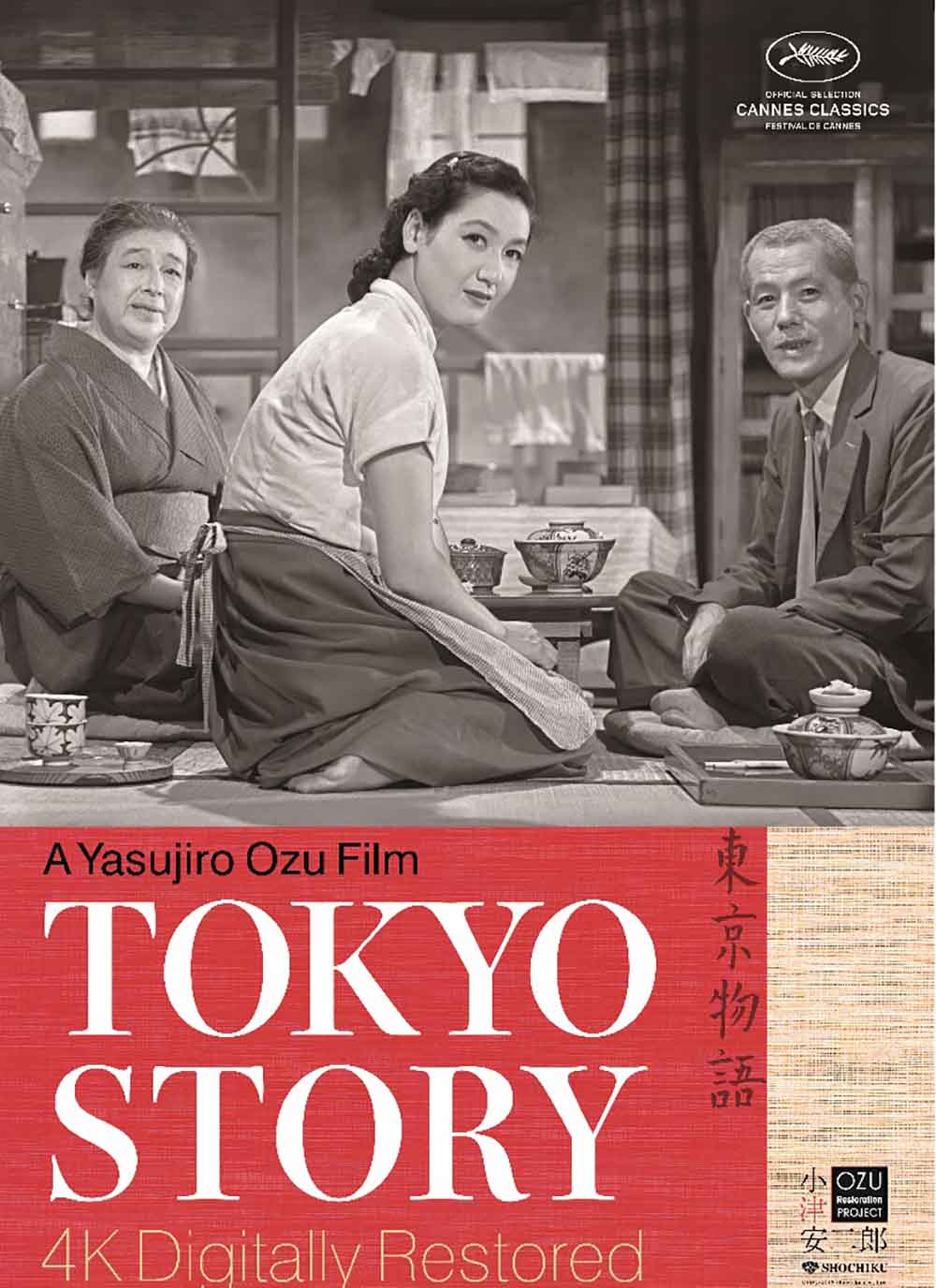
ただし、フランスでは吹替が主流なので、この時は「アニメならフランス語でも筋が分かるかな」と考え、宮崎駿の作品を選んだ。タイトルは、“Service de Livraison de Kiki”。Kiki とあるから、『魔女の宅急便』だなと思いつつ、水曜の午後に街の北にあるシネコンに向かった。どうやら、毎週水曜日にこの映画の上演があったようだ。
そして映画に関してもうひとつ、この時のパリ訪問で魅せられたことがあった。
映画館である。
『パリスコープ』をつぶさに見ていると、細田守の『時をかける少女』が上映されていることが分かった。しかも吹替ではなく、字幕上映だ。前年公開されたこの作品を、私は観逃していた。なんと、パリでキャッチアップできるとは! 興奮した。
小屋は、Studio des Ursulines。
場所は名門ソルボンヌ大学の近く、Ursulines通りにあるキャパ122人のこじんまりした劇場である。『時をかける少女』の上映は夜だったが、昼間には『地獄の黙示録』の再編集版を上映していた。
古風なチケットボックスで、いかにも映画が大好きという感じの青年から切符を買い、シアターに足を踏み入れて驚いた。
真紅のシート、2階席もあってバルコニーになっている。その曲線の美しいこと。場内の照明も心地よい。
なんだか、懐かしい感じがした。
私の故郷、宮城・気仙沼にあった旭映画劇場の記憶とクロスオーバーしたのだ。
この劇場こそ、私の世代が幼いころにイメージしていた「映画館」そのものだった。
懐かしさを覚える異国の映画館で観た『時をかける少女』もまた、素晴らしかった。
この映画は、後になって何度も観たほど大好きな一本だが、パリで観た感激は再現できない。
なぜだったのだろう?
パリに来てから、フランス語が飛び交う中で、知らず知らずのうちに疲弊していたのかもしれない。街角で飲むカフェオレやワインは素晴らしい。しかし、己の言葉の拙さゆえ、コミュニケーションを図れないストレスを強く感じていた時期だった。
そんなとき、故郷を思い出させる映画館で遭遇したのが字幕版の『時をかける少女』だった。
言葉に飢えていた私にとって、パリで聞く日本語の台詞はすべて切なく、この映画の持つ繊細な魅力が私の体の中ですぐさま発酵していった。
エンドロールが終わって、しばらく席を立てないほどの衝撃があった。
この時の映画体験を、もう超えることはないかもしれない。

この時の体験が強烈すぎたせいだろうか、2017年にパリに立ち寄った時も映画に足を運んだ。
時代は変化し、残念ながら『パリスコープ』は前年の2016年に廃刊、51年の歴史に幕を下ろしていた。
宿の近くの映画館を探していると、「シネマテーク・フランセーズ」があった。古くはヌーヴェル・ヴァーグとも関わりの深い、映画遺産の保存を目的とした施設だ。上映中の映画のタイトルを探っていくと、なんと小林正樹の『怪談』がかかっていた。東京でも滅多に観られない一本だ。
1964年公開で、183分の長尺。「長いかな」と思ったが、心配は要らなかった。三國連太郎、新珠三千代、仲代達矢、岸惠子らの演技には鬼気迫るものがあり、すっかり見入ってしまった。
パリの映画体験は、いつも記憶に刻まれるものばかりだ。
いまでも時々、シネマテーク・フランセーズのホームページを覗いてみる。
今年はゴダール、そしてアルフレッド・ヒッチコックの特集が組まれている。
それだけでも、パリに行ってみたいと思う。
パリの映画館で観る映画は、いつだって人生に彩りを与えてくれるからだ。
(※ヌーヴェル・ヴァーグ…1950年代末にフランスで巻き起こった映画運動。ゴダールやトリュフォーらが中心となって、自由で斬新な作家主義的スタイルを切り開き、映画製作に革命をもたらした。)
- 映画は世界の窓。 気仙沼で『燃えよドラゴン』、有楽町で『炎のランナー』、渋谷で『いまを生きる』…街に出かけること込みで「映画体験」!
- NYを映画で散策!『タクシードライバー』『アニー・ホール』から『ジョーカー』『モダン・ラブ』まで。この街に活気が戻ることを祈って
- パリで日本映画を観る! 『時をかける少女』『魔女の宅急便』…すると思いもよらない人生最高の映画体験が待っていた!
- 『トレインスポッティング』に、最高の朝食!ラグビー強豪国・スコットランドの首都エディンバラってどんな街?
- 寅さんが放浪し、『第三の男』の舞台となったウィーン。海外に出かけたときこそ、映画館を訪ねるといい
- ブリジット・ジョーンズやシャーロック・ホームズのように暮らし、ハリー・ポッターの世界を歩く。生活してみたくなる街ロンドン
- 洗練された街、サンフランシスコは橋が美しい。映画『ダーティハリー』、ゴールデンゲートブリッジ、「Anchor&Hope」
- 政治とジャーナリズムの街、ワシントンDCが舞台の映画たち。展開されるドラマは、最高のエンタテイメント!
- ビル・ゲイツがナチョス片手に野球観戦! リベラルな街、シアトル『めぐり逢えたら』
- LA舞台の映画は“フリーウェイ”に注目すると100倍面白い!
- 野球天国、ボストン。負け続ける球団にこそ、心躍る物語があった『2番目のキス』







