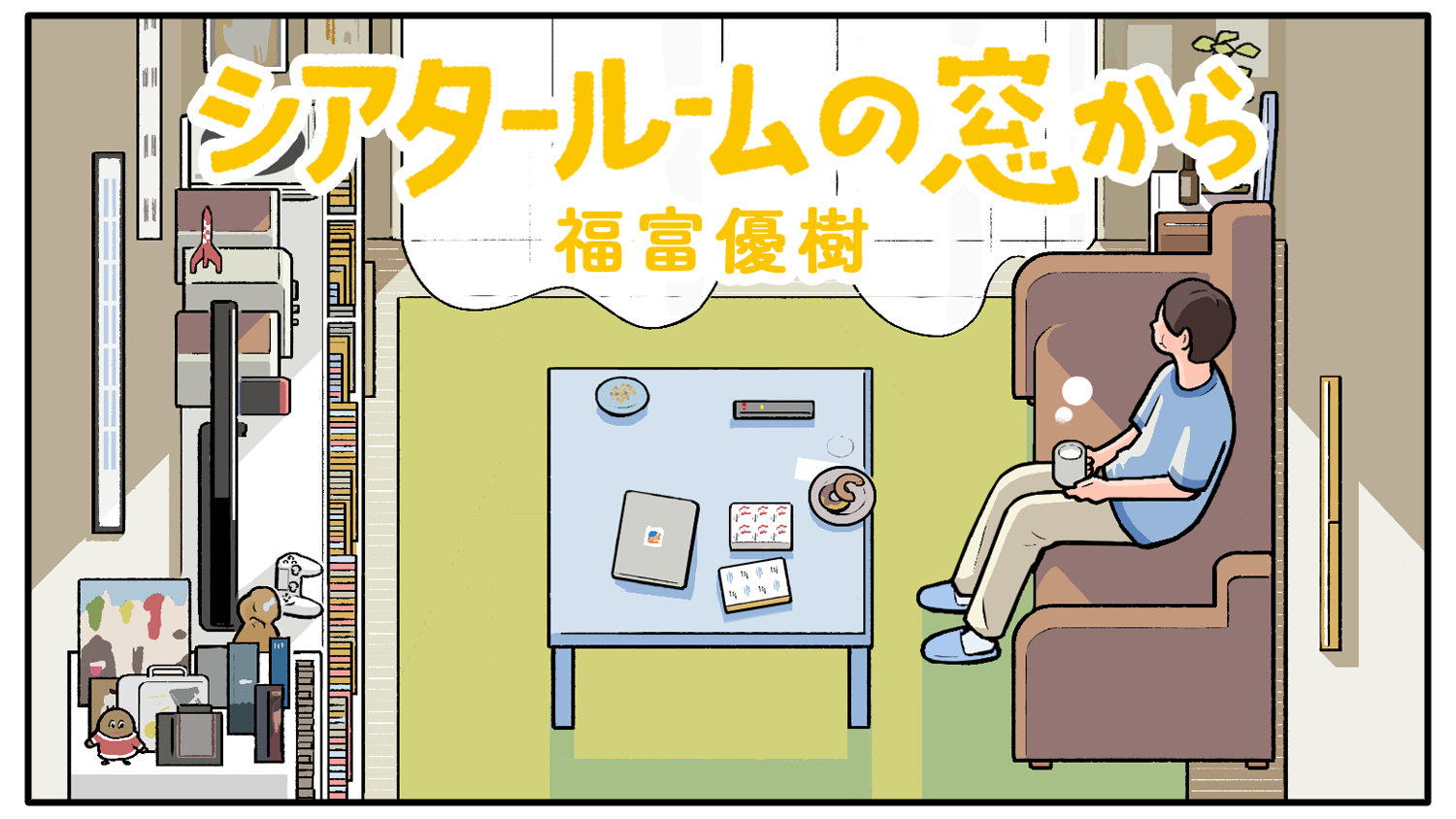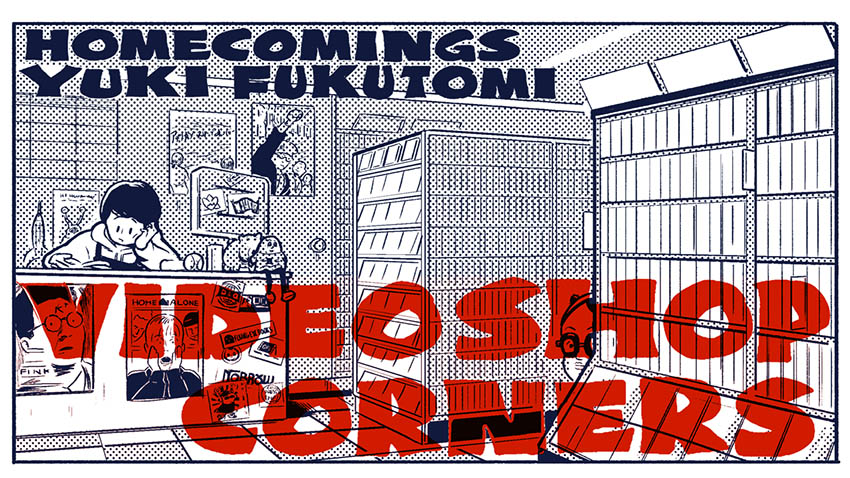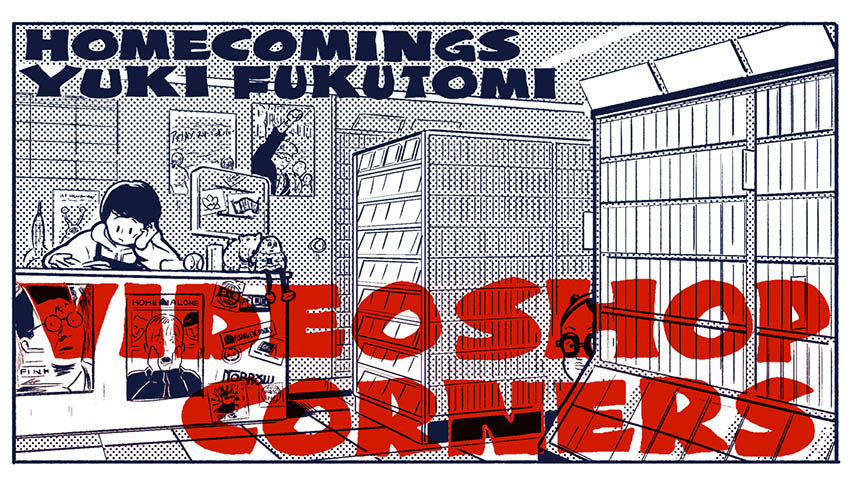目次

街並みのようなDVD棚から
創作のヒントをつまんでいく
大きな川や、いくつもの坂道がゆったりと連なる静かな住宅街。風通しのよい窓から差し込むやわらかい日差しが、室内にある大きな本棚を照らしています。背の高さほどあるその本棚には、佇まいを揃えて並べられ、「いつもの居場所」として心地よさそうに収まっている小説やCD。そのどれもが、昨日今日置かれたものではなく、持ち主と一緒に長く月日を重ね、大切にされてきたことがひと目でわかります。
その下二段にぎっしりと収まっているのが、映画のDVDやブルーレイです。

今回ご紹介するのは、映画『リズと青い鳥』(2018)や『愛がなんだ』(2019)の主題歌も手掛けた4ピース・バンド、Homecomingsの福富優樹さんのDVD棚です。PINTSCOPEのコラム連載「シアタールームの窓から」と「ビデオショップ・コーナーズ」では、大切な場所と映画にまつわるエピソードを、詩や写真とともに綴ってくれています。
9年間住んでいた京都を離れ、東京に生活の拠点を移しても、変わらずに部屋の棚に並んでいるたくさんの映画。大切な映画が揃えられた大きな棚は、福富さんが音楽や物語を作り出していく時、どのような存在になっているのでしょうか?

「京都にいた時は、ベッドやテレビ、楽器がぎっしり並ぶ部屋に2つの大きな本棚という、余白のまったくない6畳1Kの部屋に、座るか寝るしかないという生活でした。それを9年ぐらい続けていたんですけど、東京に引っ越すという大きな転機があったので、物に囲まれる生活をやめてみようと思ったんです。それで、本とかDVDを友人に譲ったり配ったりして、たくさん手放してから東京に来たんですけど…いざ暮らし始めると、やっぱり空間を埋めたくなってしまって…結局、京都にいた頃の倍の量になっちゃいました(笑)」
ひとつ何かを好きになると、その周囲にあるものが全部ほしくなってしまうという福富さん。スチュアート・ダイベックの小説『シカゴ育ち』は、海外版の原作本も購入したり、映画『マリッジ・ストーリー』(2019)やドラマ『ストレンジャー・シングス』などの日本ではDVD化されない動画配信サービスのオリジナル作品は、サウンドトラックのレコードやグッズなど、別のかたちでそばに置いたり。好きな作品は、パッケージごとにデザインを変える、その佇まいも含めたすべてを手元にほしくなるのだそうです。

「棚を自分の好きなもので埋めたいという気持ちがずっとあって。これはもう一生変わらないんだろうなという気がします」と、棚を見上げる福富さん。
「部屋で歌詞を書く時とか、漫画の原作を考えたりする時に、ヒントをたくさんもらうんです。背表紙に見えるタイトルから、この言葉いいなと思うこともあります。迷った時に、この棚を眺めたら、何かしらのヒントをもらえるという安心感があるんです。しかも、表面的に見えている言葉だけじゃなくて、棚に並ぶひとつひとつの作品に奥行きがある。例えば、“バケツ”という単語から想像を広げようとする時に、棚を眺めていると、いろんなバケツの風景が浮かんできます。ここに置いている本や映画がひとつひとつの街で、いろんな街が棚に並んでいる感じ。それぞれに住人がいて、世界があって。そこから、ヒントをつまんでいくんです」
作り手としての知的好奇心を広げ、安心感も与えてくれるというDVD棚。たとえば将来、音楽を作ることをやめたり、年を取って表現から離れる日が来たりしたら、この棚も今とはまったく違って見えてくるのではないか、と言います。そして、そうなることを寂しく思うのではなく、自分の好きな世界が並ぶこの棚との、「新しい関係のスタート」として、楽しみにしているのだそうです。

そんな大きな棚の前に座った時、目線の高さにちょうど並んでいるのが、映画のDVDやブルーレイです。カラフルなデザインにシンプルな英字タイトルで揃えられた、『ディズニー/ピクサー 20タイトルコレクション』、NYインディーズ映画界の名匠として名高いハル・ハートリー監督の作品群など、制作スタジオや監督ごとに揃えられた一角。同じ背の高さで並んだブルーレイ、黄色や赤など、どことなく配色でまとめられたDVD。その置き方の隅々に、ここにある映画をどれだけ大切にしてきたか、という思いが感じとれます。
福富さんにとって、映画を観る時間は、どのように自分の暮らしに寄り添ってきたものなのでしょうか。
初めて名前を覚えた映画監督は、スティーブン・スピルバーグ。子ども時代の福富さんにとって、映画は娯楽としてそばにあるものでした。その楽しみ方に変化が出てきたのは、中学生に近づき、音楽にのめり込んでいった頃から。CDのブックレットを隅々まで読んだり、好きなアーティストの音楽を時間軸に沿って聴いたり、という楽しみ方を、映画にも当てはめるようになったそうです。
「好きな監督の映画を、制作された順に観てバイオグラフィーを楽しむとか、ルーツを辿るとか。観て楽しむことに加えて、作り手に対する興味も出てきたんです。“クエンティン・タランティーノ監督は、いろんな要素をサンプリングしていくヒップホップと似ているのな”とか、音楽に置き換えて考えたり。映画を文脈的に楽しむようになったのは、音楽を好きになったことの影響が大きいです」

石川県に住んでいた当時、映画について一緒に話す友だちは周りにいなかったと言います。でも、だからこそ「僕だけのもの」という感覚が強く、自分にとって映画が特別なものになっていったのです。そこから生活の拠点を移し、京都の大学に進んだことで、福富さんと映画の関係は、また少し変化していきました。
美術系の学部と人文系の学部が、小さなキャンパス内に混在していたという大学。そこには、「情報館」という図書館のような施設があり、地下には、DVDやVHS、レーザーディスクなど、様々な形に閉じ込められた映画がたくさん並んでいたそうです。その鑑賞用スペースで、大学にいるほとんどの時間を福富さんは過ごしました。
「ウェス・アンダーソンもガス・ヴァン・サントも、本当にたくさんの映画を、僕はその場所で初めて観ました。でも、同時にすごく良かったのは、いわゆるシネフィルが好みそうな映画だけじゃなくて、世間で流行した映画とか、アイドルが出ている映画とか、どんなジャンルの映画も並列に置かれていたことなんです。『地獄の黙示録』(1979)の近くに『そんな彼なら捨てちゃえば?』(2009)が置いてあったり(笑)。それをみんなが、当たり前のように行き来して楽しんで観ている。映画に対しての、“僕だけのもの”という少し閉じた卑屈な感じが和らいだのは、ここの映画のラインナップがかなり影響しています」

大学を卒業して京都市内に引っ越してからは、「街中に、映画館が10箇所ほど点在していた」という環境もあり、暮らしの中で、映画を観るという時間がさらに増えていきます。
「どこかに出かけたついでに観るとか、外出先の選択肢の中にいつも映画館が入っていました。映画館に行っても別にTwitterで呟かないみたいな(笑)。それくらい普通のことで、ご飯を食べに行くように、衣食住の中に含まれていました。新作の公開も、まずは東京から始まって、京都の映画館で上映されるまで少し時間差があるんですけど、自分の近所の映画館にいつ頃来るというのをチェックして、カレンダーに書き込むとか。映画がやってくるのを待つ、その時間も楽しかったです」
そんな京都での暮らしを離れ、福富さんは一年ほど前に東京に引っ越してきました。上映が自分の街にやってくるのを待つこともなく、公開当日から観たい映画がすぐに観に行ける環境にはなりましたが、生活のすぐ近くに映画館があった京都のように、週に何度も足を運ぶことはなくなったそうです。それでも、大きな川を渡り、自転車で20分かけて少し離れた街に映画を観に行く、その道程も含めて今の暮らしを気に入っているといいます。

「ご飯を食べたり散歩をしたり、僕は衣食住が全部好きなんです。“何かを好きになること”が好きだから。自分が生活している街にも好きな場所をたくさん見つけたいし、行ったお店や見た景色とかも、全部覚えておきたい。その“忘れたくない”という気持ちが強いのは、石川から京都、東京と、住む場所を転々としてきているからだと思います。離れてきた場所が多いからこそ、それぞれに思いが残るし、好きだった記憶も覚えておきたいんです」
福富さんの書くコラムには、好きな映画への想いだけではなく、映画を観た日に立ち寄ったお店や食べたもの、その日の天気など、映画のまわりに纏っているもすべての記憶を愛おしむようなまなざしがあります。住んでいた街や、当時のことを覚えていたいという思いの中で、映画を観る時間は、記憶を纏う日記のようなものなのかもしれません。
「僕は、“今が一番いい”といつも思っているので、あの頃に戻りたいとか後ろ向きな気持ちがあるわけじゃないんです。でも、好きだった場所とか昔の記憶を覚えていることで、前向きに進めることもあると思う。そういう時、日記やメモがなくても、映画を観ると、記憶が紐解かれていくので、DVDという形で手元に置いておきたいという思いもあります」

映画にそうしてもらったように
優しさが残る音楽を作りたい
誰か個人の物語でありながら、語り手のような距離感で誰にでも寄り添ってくれる、Homecomingsの楽曲。登場人物の住む街や見ている景色にまで、自分の世界が広がるような歌詞、アメリカ郊外の都市をイメージするようなアートワークなど、どこか映画のような、物語を感じる奥行きがあります。福富さんを含め、バンドのメンバー全員が映画好きなことでも知られ、Homecomingsのアートワークを手掛けるイラストレーターのサヌキナオヤさんと、映画上映とバンドのライブ、ZINEの制作が一体となったイベント「NEW NEIGHBORS」を開催するなど、福富さんの作る音楽のそばには、いつも映画の存在が感じられます。
映画のタイトルや、その世界観からヒントをもらうことに加えて、作り手である、好きな映画監督の姿からも影響を受けることはあるのでしょうか? そう尋ねると、DVD棚からウェス・アンダーソン監督の『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』(2001)のコレクターズ・エディションボックスを出してくれました。

「ウェス・アンダーソンの映画が昔から大好きなんです。アメリカ以外の文化も入れていくサンプリングみたいな感覚とか、ポップさを失わないまま、あっと驚かせてくれるところとか。メジャーになりすぎずに、ずっとインディーズのような遊び心を持っているところも、絵の強度を大事にしているところも好きで。同じ理由でいうと、僕はコーエン兄弟の初期の作品とかも大好きなんです。でも、毎日名前を検索して、なにか新しい情報がないかなーと探すほど追いかけているのは、ウェス・アンダーソンですね」
大学時代に、情報館で初めて観た『ザ・ロイヤル・テネンバウムス』。その物語の中で使われていた音楽、ニコの「These Days」は、Homecomingsのライブで、ステージの照明が落とされる始まりの瞬間に、昔も今も流れています。そうした劇中に流れる音楽や、メイキング映像に収録された現場での姿など、ウェス・アンダーソンの映画を作り出すすべてが、ものづくりを続ける福富さんを支えてきたといいます。

「ちょっと世界を立体的にしたいというか、噛んだ時にいろんな味がするような音楽にしたくて。曲だったら、何か新しい要素を試そうとミックスの時にノイズを入れてみたり、CDのジャケットだったら、隠し絵を作って、世界が広がるように遊び心も入れたり。そういう“奥行き”を求める、という感覚は、ウェス・アンダーソンの影響です。あと、一番憧れるのは、自分の作品に対して絶対に妥協しない、徹底してこだわる姿です。どのカットを観ても、細部まで監督の魂が入っていることがわかる。僕も、自分の音楽やものづくりに関しては、全部に自分の意思を通したいし、ひとつもほったらかしにしたくないと思っているんです」
どれだけ規模が大きくなり環境が変わっても、自分の世界を手放すことなく持ち続けているウェス・アンダーソン。その姿に憧れ、曲やCDのアートワークなど、表現するすべてのものに細部までこだわるHomecomingsの音楽は、ひとつの完成された世界を持ちながらも、どんな人のそばにもいてくれるような温度を持っています。ここ数年では、『リズと青い鳥』や『愛がなんだ』などのエンディング曲も手掛け、映画が終わった後、暗闇でエンドロールを眺める観客の余韻に寄り添いました。
「仕事として関わる機会が増えても、映画の楽しみ方は変わっていないんです。“これは仕事につなげたい”みたいな目線で映画を観ることもないし。でも、音楽を作る時に昔から思っているのは、映画を観た後の、言葉にならない気分を曲にしたいなぁということ。特大のヒットソングを作りたいとか、たくさんの人に聴いてほしいというよりも、僕の好きな、『トゥルーマン・ショー』(1998)や『サムサッカー』(2005)、『レディ・バード』(2017)を観た後に感じる、切ないような優しい気持ちになるようなあの感覚。それをうまく言葉にできないから、音楽で表現したいんです」

ダンスミュージックを作る人が、自分の曲で踊ってほしいと思うように、自分たちの音楽を聴いてくれた人には、何かしらのいい作用があってほしい。そしてそれが、辛い時や寂しい時、そっと隣にいてくれた好きな映画たちのように、心地よい距離感で聴く人に寄り添うものであってほしい、と福富さんはいいます。
「何かに優しくなれるような、優しくしてもらった気分になれるような音楽が作れたらいいなと思うんです。僕も、自分の好きな映画にそうして寄り添ってもらった記憶がたくさんあって。たとえば、スパイク・ジョーンズの『かいじゅうたちのいるところ』(2009)は、ひとりで寂しさを抱えている少年が、同じようにどこか寂しさを抱えているかいじゅうたちと出会う話なんですけど、“大丈夫だよ!”というのではなく、“僕も同じだよ”という温度で一緒に過ごすことで、最後は少しだけ感情に雪解けがあって終わるんです」
そしてもうひとつ、優しさについて描かれたある映画を棚から出してくれました。福富さんがサヌキナオヤさんと一緒に開催している上映イベント「NEW NEIGHBORS」でも上映したことのある映画『スモーク』(1995)です。ニューヨークのブルックリンを舞台に、いくつかの寂しさや、問題をかかえた登場人物たちの人生が交わっていくこの群像劇は、“ひとつの街を舞台にした映画のサウンドトラック”をコンセプトに作られたセカンドアルバム『SALE OF BROKEN DREAMS』など、Homecomingsの音楽にもつながる大切な一本でした。

「ブルックリンに住むいろいろな人たちが、それぞれに優しさを分けあっているというストーリーなんですけど、僕のものづくりの中でひとつの指針になる作品です。物語の中でひとつの街が大事な要素になっているところも、つながるかもしれません。クリスマスという、一年の中でもちょっと寂しさが募る時期を描いているところも好きですね。だからこそ、優しさが心に残るのかなと思います」
これまで、毎年クリスマスの時期に小さなツアーを行ってきたHomecomingsですが、今年は、クリスマス当日の25日に「Blanket Town Blues」というイベントを開催します。会場での公演と、その様子をオンラインで届ける生配信、後日に配信するディレクターズカット版と、現地でも自宅でも、3つの方法から楽しめるようになっています。今年は、日常が変わり、不安や寂しさなどさまざまな感情に覆われた一年だっただからこそ、その終わりの寒い夜に、気持ちが温まるようなライブになればと、福富さんは言います。
「クリスマスって、楽しい日でもあるけど、どこか寂しくなる一日でもあって。本当はそんなこと思う必要はないんだけど…ひとりで街に出るのが寂しいとか。今年は家でも楽しめる企画にしているので、誰かといてもひとりでも、みんなが楽しめる日になればと思っています。ライブやイベントがなかなかできない、もどかしい一年ではあったけど、必ずしも現場で体験しなくても、自分の部屋でも楽しむ方法があるという可能性が広がった年でもあると思うんです。それは映画にしても、音楽の楽しみ方にしても。そういう選択肢が増えたことを楽しんでいけたらいいですよね」

当日は、オンライン配信での魅せ方もふくめて、映画的な演出も企画しているというHomecomingsのクリスマスライブ。街並みや自分の暮らしが変わり続けても、寂しい時や、ものづくりに向き合う時、DVDを再生すればいつも当たり前のようにそばにいてくれた大切な映画。それと同じように、福富さんの作る音楽や物語が、きっとこれからも誰かの隣に居続けるのでしょう。
- 映画に込められた愛情と熱量が 自分の「好き」を貫く力になる
- 「好き」が詰まった部屋はアイディアの引出し
- 映画を作るように、料理を作りたい。働き方の理想は、いつも映画の中に
- 最新技術と共に歩んできた映画の歴史から、“前例のない表現”に挑む勇気をもらう
- 映画は仕事への熱量を高めてくれる存在。写真家のそばにあるDVD棚
- “これまでにない”へ挑みつづける!劇団ヨーロッパ企画・上田誠が勇気と覚悟をもらう映画
- “好き”が深いからこそ見える世界がある!鉄道ファンの漫画家が楽しむ映画とは?
- 一人で完結せず、仲間と楽しむ映画のススメ
- おうち時間は、アジア映画で異国情緒に浸る
- 漫画家・山田玲司の表現者としての炎に、火をくべる映画たち
- 時代の感覚を、いつでも取り出せるように。僕が仕事場にDVDを置く理由
- 「この時代に生まれたかった!」 平成生まれの役者がのめりこむ、昭和の映画たち
- 好きな映画から広がる想像力が 「既視感がバグる」表現のヒントになる
- 好きな映画の話を相手にすると 深いところで一気につながる感覚がある
- 勉強ができなくても、図書館や映画館に通っていれば一人前になれる。
- ナンセンスな発想を現実に! 明和電機とSF映画の共通点とは?
- 22歳にして大病で死にかけた僕。「支えは映画だった」 絵本作家の仕事部屋にあるDVD棚
- 映画は家族を知るための扉。 保育園を営む夫婦のDVD棚
- 「映画を観続けてきた自分の人生を、誰かに見せたい」 映画ファンが集う空間をつくった、飲食店オーナーのDVD棚
- “すべての人を肯定する服作り”をするファッションデザイナーのDVD棚
- 「データは信用していない」映像制作プロデューサーが、映画を集める理由
- 写真家としてテーマを明確にした映画。自分の歩む道を決めてきた、過去が並ぶDVD棚。
- DVD棚は“卒アル”。 わたしの辿ってきた道筋だから、ちょっと恥ずかしい
- 映画を通して「念い(おもい)を刻む」方法を知る
- 家にいながらにして、多くの人生に出会える映画は、私の大切なインスピレーション源。
- オフィスのミーティングスペースにDVD棚を。発想の種が、そこから生まれる
- 映画の閃きを“少女”の版画に閉じ込める
- 映画の中に、いつでも音楽を探している
- 映画から、もうひとつの物語が生まれる
- 探求精神があふれる、宝の山へようこそ。
- 無限の会話が生まれる場所。 ここから、創作の閃きが生まれる。
- 夢をスタートさせる場所。 このDVD棚が初めの一歩となる。
- 本や映画という存在を側に置いて、想像を絶やさないようにしたい。