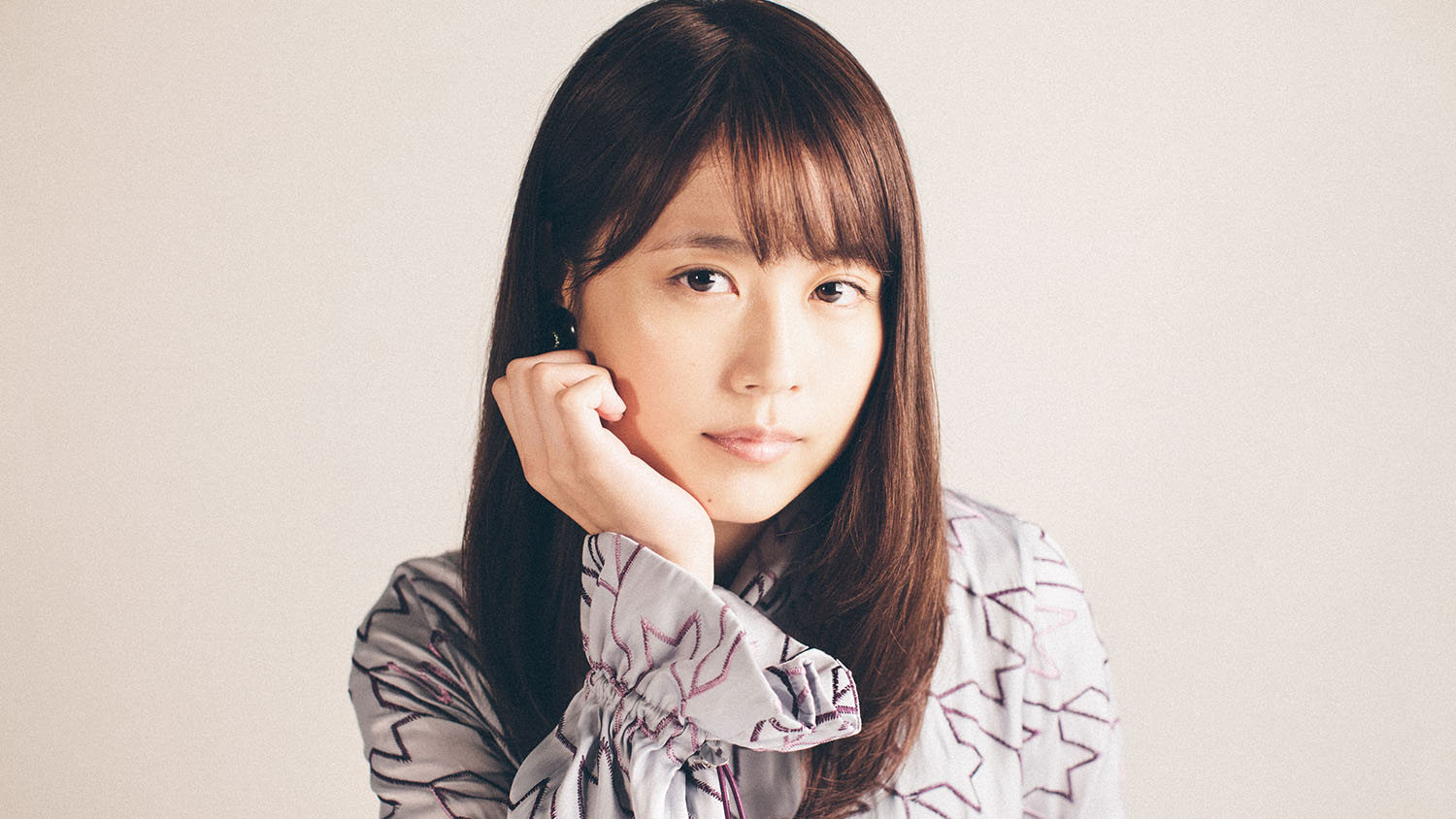僕は、映画を観る時、全く芝居を観ていない。たまに友達と一緒に映画を観終わった後に言われる「あそこのあの芝居、良かったよねえ」という言葉に冷めてしまう。うるさい。うるさい。まだ頭の中が映画の中にいるのだ。だから、せめてその話はこの後立ち寄る公園で缶ビールを持つまで待ってくれ、この帰り道くらいは話さないでくれ、という気持ちになるのだ。なので、基本的に友達とは映画を観たくない。もちろん映画を観る時に、芝居に注目するのは構わない。否定したいわけじゃなく、僕は観ないのだ。それだけの事だ。
そもそも芝居が上手いとは、どういう事なのだろう。いくら考えても分からない。僕は映画を観ていて、「この役者、芝居が上手だ」と感じ取ってしまった瞬間、気持ちが冷めてしまう。それは、映画の中から急に追い出されて、芝居をしている役者としての意識が生まれてしまうからだ。そんなもの、映画を観る時に必要ない、と僕は思う。
僕は映画を観る時、何を観ているのだろう。「画面を観る」ことしかしていない気がする。芝居、風景、音、物語、全て感じてはいる。けれど、最初からそれら目当てで映画を観に行くということを僕はしたくない。映画という一つの芸術に純粋に出会いたいのに、役者という一つのフィルターに邪魔されている気がするからだ。
ふと思ったのだけど、脚本家の人は映画を観る時に、物語に注目して観るのだろうか。観ない人もいるのだろうか。もう訳が分からないので、考えるのをやめる。
そんな中、僕が毎回芝居を観てしまう数少ない映画がある。
レオス・カラックス監督の『ホーリー・モーターズ』。主人公のオスカーは、演じるという仕事をしている。正直、劇中劇だから芝居を観てしまうのかもしれない。オスカーの芝居を観ているのか、オスカー役を演じたドニ・ラヴァンの芝居を観ているのか、分からないところだけど、とにかく、芝居を観てしまう大好きな映画だ。
オスカーが演じる中でも、好きな役がある。メルド。フランス語で「クソ」という意味を持つ怪人だ。
ヘアメイクも、ファッションも、特殊メイクも、全てが不気味だ。身体中の関節の動き、そしてその速さ。リズムが人間ではないのだ。途中で、タバコを反対向きで吸おうとするのだが、画面を停止させないと見えないくらいのスピードで、フィルターの部分を切り取り、捨てるのだ。まず考えたのは、これは演出なのか。アドリブなのだろうか。それとも美術部が、フィルターの部分を、切りやすくしておいていたのだろうか。それとも、ドニ・ラヴァンがその技を習得していたのか。
なぜ、タバコを親指に挟んで吸うのか。それは爪が長いからだ。人差し指と中指に挟んで吸ったら、爪が顔に刺さる。自然な事なのだ。
とにかく、メルドの奇妙さを確かに増やしているシーンだ。
メルドのメイクを拭き取り、次にオスカーが演じる役は、アンジェルという女の子の父親だ。
顔にはシワが追加されてあり、髪の毛は白髪。衣装は地味で、ハットを被っている。
車で音楽を流す。きっとこの音楽は、この父親がよく聴く曲なのだろう。
父親を演じるオスカーにとってこの曲は、気持ちを切り替えるスイッチの様な役割を果たしているのだろうか?
確かに、僕も芝居をする時、衣装や、現場の音で、気持ちを切り替える事がある。自分の想像していた姿や、空間を、徐々に体感に変えていくのだ。
演じる仕事をしているオスカーが、気持ちを切り替えるためスイッチの様な曲を流す。それをドニ・ラヴァンが演じていて、レオス・カラックスが映画を撮っている。もう、訳が分からない。レオス・カラックスは、僕を劇中劇やメタフィクション(※)の深い思考の闇に放り出した。ああ、最高だ。
アンジェルは、人生初めてのパーティーが楽しかったと父親に嘘をつく。
それに気付いた父親は、娘に
「ウソを後悔してるか?」と聞く。
「してる」
「バレないと思ったらまたウソをつくか?」
「たぶんそうする」
「なぜだ」
「その方が幸せだから。」
娘が言い終わり、父親はタバコを吸う。そして遠くを見るのだが、その目には、溢れそうで溢れない涙がいる。父親の涙だ。本当に、なんて芝居なんだ。
この後もオスカーは、何役も演じていく。
僕にとってこの映画は、大好きな映画でもあり、勉強になる映画なのかもしれない。芝居をする時の発見が、いつも見つかる映画だ。
最初に、芝居が上手いと感じた瞬間に、気持ちが冷めてしまうと書いたが、上手い下手に関わらず、無意識で、映画の中にいるその人間の存在に納得していれば、何も問題なく観る事が出来る。そして、そういう役者に僕はなりたい。
しかし、面白い事に、ここまで芝居について書いてみたが、どれだけ芝居がいい作品を観ても、映画として好きではなかったら、その芝居の記憶はほとんど残らなかったりもする。
映画があって、芝居がある。映画が好きだから映画を観る。
僕はいつまでもそんな風に、映画と純粋に関係していきたい。



※:映画や小説、アニメなどの創作物において、作中の架空の出来事であるフィクションを、意図的に「作り話」として表現する手法。